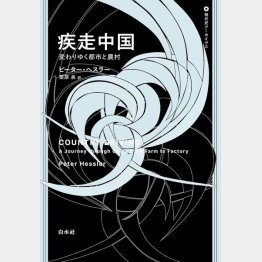人生の転変をめぐる感慨へと誘う主人公の変化
「新世紀ロマンティクス」
「芸といふものは実と虚との皮膜の間にあるもの也」とは近松門左衛門の「虚実皮膜」の芸術論。この言葉を地でゆく映画が先週末封切りの「新世紀ロマンティクス」である。
北京五輪を翌年に控えた中国の地方都市。しがないCMモデルのチャオと恋人でマネジャーのビンが、ちっぽけなイベント仕事にいそしむ。やがて「一旗揚げる」の一言で消えたビンを追って各地をさすらうチャオ。行き先の街が大同、奉節、珠海とうつろうなかであっというまに時が過ぎ、素朴で垢抜けなかった中国が、まるでバブル時代の日本のように平板で軽薄な顔つきに変貌してゆく。
初めは小娘のようだったチャオもうたかたの中に年を重ね、スーパーでレジを打つ疲れた中年女になってゆく。この変化が胸の奥底にしみて、月並みな感動とは違う人生の転変をめぐる感慨へと見る者を連れ出すのである。
実は主役の趙濤(チャオ・タオ)は監督の賈樟柯(ジャ・ジャンクー)作品の常連で、私生活でも夫婦の仲。そのため本作では過去作品の未発表映像が引用と再編集で新しい物語へと編み直されている。本作でチャオがしだいに年を重ねるのはリアルな時間のたまものなのである。虚実のあわいとはまさにこれだろう。
かつて中国映画「第六世代」の若手だった監督も既に50代半ば。天安門事件の衝撃を真正面にくらった世代の「いま」をのぞかせる一作だ。
急激な経済成長途上の中国に暮らしたアメリカ人記者のルポ、ピーター・ヘスラー著「疾走中国」(栗原泉訳 白水社 3960円)は映画と同時期の地方都市を活写する。本書で見る20年前の中国はバブル三昧とも違う愛すべき国。礼賛でも批判でもない地道でリアルな練達の中国ルポは2011年に邦訳され、復刊を望む声に推されて昨秋再登場した。不思議に高度成長期の日本を思い出させるのも面白い。
<生井英考>