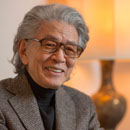五木寛之 流されゆく日々
-

連載11369回 「非常識健康論」のすすめ <4>
(昨日のつづき) 遠方を凝視したり、細かい文字を読んだりしたあとは、逆のことも行ったほうがいい。 ぼんやり空の雲の行き来を眺める。雲をちゃんと見ていると、その移動する速さに、あらためて驚くこと…
-

連載11368回 「非常識健康論」のすすめ <3>
(昨日のつづき) 知床で遭難した観光船乗客の捜索がきょうも続いている。コロナ、ウクライナ、海難事故と、つらいニュースの連続で、自然と心も萎えてくる日々の連続だ。 疫病、戦争、事故となると、ふだ…
-

連載11367回 「非常識健康論」のすすめ <2>
(昨日のつづき) ボケのはじまるきっかけは、情報の遮断である。見る、聞く、触る、この3つの働きが遮断されると、まずいことになる。 視力をどう維持するか。 老眼鏡を使えば、ある程度の視力はお…
-

連載11366回 「非常識健康論」のすすめ <1>
昨日、<日刊ゲンダイ>の読者を自称する友人から、 「こないだ『常識的健康論のすすめ』というやつを読んだけど、ぜんぜん常識的じゃない。あれはやっぱり『非常識健康論のすすめ』でやるべきだ」 と、文…
-

連載11365回 「常識的健康法」のすすめ <10>
(昨日のつづき) 先週と今週、10回にわたって<咀嚼>と<嚥下>について書いてきた。これは健康に関する入口のあたりである。「噛む」と「飲みこむ」は一体の仕事だ。そのためには、舌が大きな働きをしてい…
-

連載11364回 「常識的健康法」のすすめ <9>
(昨日のつづき) 私の健康に関する練習は、必ずしも世間でいう健康のためではない。養生という表現のほうがぴったりくる一種の趣味である。道楽、といってもいいだろう。 面白いからやる。興味があるから…
-

連載11363回 「常識的健康法」のすすめ <8>
(昨日のつづき) 話をもどして「飲み込む力」の問題だ。だれも気にしない「飲み込む力」について、私はかなり長い間、自己流のトレーニングを続けてきた。 言ってみれば「嚥下力」とでもいうような作用で…
-

連載11362回 「常識的健康法」のすすめ <7>
(昨日のつづき) 週刊誌、新聞、そして単行本も含め、いわゆる健康情報が氾濫している中で、私たちは立ち往生しているというのが実態だろう。 それぞれ医学や栄養学、はては他の分野の専門家をまじえて、…
-

連載11361回 「常識的健康法」のすすめ <6>
(前回のつづき) 「噛む」に続いて「飲む」技法について考える。 私たちは物を飲みこむときに、ことさらその過程を意識することがない。なにげなく無意識に飲みこんでいるのである。 「ちゃんと噛む」こ…
-

連載11360回 「常識的健康法」のすすめ <5>
(昨日のつづき) さて、ものを飲み込むという作業を、私たちはどのようにやっているのだろうか。 ほとんどの場合、私たちは無意識にその行為を行っている。 喋りながら飲みこむ。テレビを見ながら飲…
-

連載11359回 「常識的健康法」のすすめ <4>
(昨日のつづき) ちゃんと噛むということは、やさしいようで結構むずかしい仕事だ。 若いうちはいいが、加齢とともに誰でも歯がいかれてくる。そのために、噛むとき左右どちらかの側に咀嚼が片寄りがちに…
-

連載11358回 「常識的健康法」のすすめ <3>
(昨日のつづき) 私の父親は学校の教師だった。 福岡県の小倉師範学校を出て、県内の小学校に奉職した。した、というのは私の推測である。その辺の事情をくわしく聞いておけばよかったと後悔するばかりだ…
-

連載11357回 「常識的健康法」のすすめ <2>
(昨日のつづき) <食ハ養生ニアリ>とは昔から言われてきた文句である。 これは健康のもとは食べることだ、という話だ。この言葉に異論のある人はいないだろう。食物は体を動かすガソリンである。最近はE…
-

連載11356回 「常識的健康法」のすすめ <1>
現代人の望むものは何か。 いろんな人に質問してみたが、結局は3つのKにおさまる。「経済」「健康」「希望」の3項だ。「経済」というのは恰好つけた言い方で、要するに「金」の問題だろう。 このなか…
-

連載11355回 様々な戦争について <5>
(昨日のつづき) 21世紀は<難民の時代>である、と繰り返し書いてきた。それはちゃんとした歴史観にもとづいた論ではない。 自分自身が難民の一人として難民キャンプに収容された経験からきた直感に過…
-

連載111354回 様々な戦争について <4>
(昨日のつづき) 自由主義の根幹は市場原理である。市場原理の根幹は平等な競争である。しかし、現代の市場は平等ではない。そこには2つの大きな格差がある。資本の格差と、もう一つ決定的なのは情報の格差だ…
-

連載11353回 様々な戦争について <3>
(昨日のつづき) 俗に隠岐騒動と呼ばれる内戦は、1868年におこった隠岐の独立戦争だった。 島民三千余人が武装蜂起し、短期間ではあっても、島民による自治政権が確立されたのだ。一種のコンミューン…
-

連載11352回 様々な戦争について <2>
(昨日のつづき) アメリカをはじめ、欧米各国の国防予算がにわかに増大しつつある。当然だろう。ウクライナの現状を見て、どの先進国の国民も、それに反対することはあるまい。 1930年代のスペイン戦…
-

連載11351回 様々な戦争について <1>
先ごろから新聞、テレビが、ウクライナの首都、キエフを<キーウ>と呼ぶようになってきた。 ロシア語読みを、ウクライナ語にあらためたのである。 チェルノブイリが<チョルノービリ>、オデッサが<オ…
-

連載11350回 リモート講演の盲点 <5>
(昨日のつづき) 先日、ふと思い立って、ブッダの生涯をあらためてたどってみた。ブッダ、いわゆる釈迦、ガウタマ・ブッダと呼ばれた人である。 神も、神の子もいないところが、仏教の仏教たるゆえんだろ…