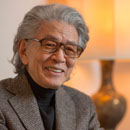五木寛之 流されゆく日々
-

連載11003回 後半50年の希望と絶望 <6>
(昨日のつづき) 先週に続いて同じテーマで書く。 ここでいう「後半50年」というのは、50歳を過ぎてからの後半50年のことだ。「人生百年時代」がほぼ現実のものとなった以上、悪くすれば誰でもがそ…
-

連載11002回 後半50年の希望と絶望 <5>
(昨日のつづき) 高齢者の習性の一つは、よく新聞を読むことである。私もその例にもれず、このところ時間をかけて新聞に目を通すようになった。 朝、毎、読、日経、産経、東京と最低6紙は丹念に読む。ほ…
-

連載11001回 後半50年の希望と絶望 <4>
(昨日のつづき) このところ立て続けにいくつかの新聞・雑誌のインターヴューを受けた。 それぞれ取材の意図はちがうが、最後に必ず同じ質問に落ちつく。 「ポスト・コロナの世界はどうなるのでしょう…
-

連載11000回 後半50年の希望と絶望 <3>
(昨日のつづき) 百寿者の数が万の単位で増大していく現在、後半50年をどう生きるかこそが、リアルな問題である。 いわゆる人生論というやつは、ほとんどが人生前半の50年について語られたものばかり…
-

連載10999回 後半50年の希望と絶望 <2>
(昨日のつづき) 「人生五十年」の時代は過ぎ、今後、私たちはいやおうなしに後半の50年を生きることになるだろう。 気の遠くなるような現実である。 ふと思うのだが、はたして長く生きることが人間…
-

連載10998回 後半50年の希望と絶望 <1>
昔は「人生五十年」と言った。 とはいうものの、誰もが50歳まで生きたわけではない。 つい明治の頃までは、日本人の平均寿命は30歳代後半だったのだ。「人生五十年」というのは、せめて50歳ぐらい…
-

連載10993回 時代の秋がやってきた <1>
ひと雨ごとに涼しくなっていく。 涼しいというより、肌寒い感じなのは夏の温度に体が慣れているせいだろう。 しまっておいた古いツイードのジャケットを発掘して羽織ってみる。さすがに分厚い上衣は、ち…
-

連載10997回 時代の秋がやってきた <5>
(昨日のつづき) 新型コロナに関して、一時は連日のように感染者の数が発表され、国民全部が一喜一憂する日が続いたものだった。 あの発表の雰囲気にどこか既視感があるような気がして仕方がなかった。よ…
-

連載10996回 時代の秋がやってきた <4>
(昨日のつづき) 高齢者の身体的機能が落ちて、日常生活にも不自由を感じるように衰えてくる現象をフレイルとかいうそうだ。 フレイルは体だけでなく、いろんな方面に現れてくる。 「オリンピック発祥…
-

連載10995回 時代の秋がやってきた <3>
(昨日のつづき) <意志の強い弱いは生まれつきである>とむかし書いたことがあった。 個性とか性格とかいうものは、どうしようもないものである。背が高いとか低いとかいうのもそうだ。走るのが速いとか、…
-

連載10994回 時代の秋がやってきた <1>
(昨日のつづき) 「秋風秋雨人を愁殺す」とかいう。 「春愁」 という言葉もあるが、愁といっても春三月の愁は、どこか暖かみのある愁いだ。 それにくらべると秋の愁いは、ひんやりと冷たい。 …
-

連載10992回 記憶の海を漂いながら <5>
(昨日のつづき) このところ不景気なニュースばかりが目につく。 <全日空 冬のボーナスなし> という記事がでていた。(10月8日・読売) <年収 3割を削減> 全日空といえば、昔はJA…
-

連載10991回 記憶の海を漂いながら <4>
(昨日のつづき) 上京しての数年間は、食うや食わずの生活だった。 文学部の地下に協同組合の売店があった。そこの窓口では、ガラスびんに入れたタバコを、1本いくらでバラ売りしていた。 「3本くだ…
-

連載10990回 記憶の海を漂いながら <3>
(昨日のつづき) 戦争が深まるなかで、食糧不足も目立ってくる。 当時は米は配給制だった。1人当り2合と何勺かである。外地では2合5勺だった時期があり、食糧不足が深刻化するなかで、さらに配給の量…
-

連載10989回 記憶の海を漂いながら <2>
(昨日のつづき) きのうか、おととい見た新聞に「饅頭」の話がでていた。あの餡のはいったマンジュウである。「万十」と書くこともあるらしい。 饅頭と書くより「まんじゅう」と書いたほうが感じがでる。…
-

連載10988回 記憶の海を漂いながら <1>
記憶は気まぐれである。 ついさっきまで憶えていた言葉が、なぜか出てこない。顔も声も、経験もぜんぶ知っている人の名前を思い出せなかったりもする。 ボケている、というほどのことでもない。若い人で…
-

連載10987回 私のファッション前史 <7>
(昨日のつづき) その頃、というのは1950年代初期のことだが、女性のあいだで奇妙なスカートが流行っていた。 裾のほうがやたらと広く開いた変ったスカートである。たしか<落下傘スタイル>とか呼ば…
-

連載10986回 私のファッション前史 <6>
(昨日のつづき) 戦後、学制改革とかいうものがあり、男女共学がスタートした。私が入学したのは前身は女学校で、校庭に藤棚があったりする落ち着いた学校だった。 夏の暑い時期をのぞいては、ほとんど一…
-

連載10985回 私のファッション前史 <5>
(昨日のつづき) ソ連軍がやってきて、すぐにそれまで住んでいた家を接収されて、市内のあちこちを流れ歩いた。一時期、大同江ぞいのセメント工場で満州からの難民と一緒に暮したことがある。 その冬は、…
-

連載10984回 私のファッション前史 <4>
(昨日のつづき) 9月、平壌に進駐してきたソ連軍は、呆れるほどの階級組織だった。上級の将校たち(連中に対しては階級に関係なく、私たちはカピタンと呼んでいた)は、市内の住宅地に夫人と共に住んでいた。…