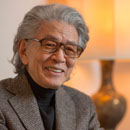五木寛之 流されゆく日々
-

連載11606回 歩くための技法 <5>
(昨日のつづき) 歳をとると、どうしても姿勢が悪くなる。前かがみになって、小股でチョコチョコ歩きになりがちなのだ。 歩く姿勢を良くするにはどうすればいいか。やたらと胸を張ってシャチこばったとこ…
-

連載11605回 歩くための技法 <4>
(昨日のつづき) いろんな解説書に、歩き方の基本としてこんなことが説かれている。 <足の運びは、踏みだした足を踵から着地するのが基本> 要するにスリ足はいけない、というわけだ。前方に振り出し…
-

連載11604回 歩くための技法 <3>
(昨日のつづき) 飛行機やクルマ、鉄道などを利用して移動しても大変だった行程を、紀元前数百年前、ブッダは徒歩で移動したのだ。 そして晩年、その旅の途上で食中毒で倒れる。彼が行き倒れた雑木林を訪…
-

連載11603回 歩くための技法 <2>
(昨日のつづき) ブッダが偉い人であったことは、よくわかっている。小国といえども支配者の地位を捨て、放浪の旅にでた。出家したわけではない。なにか新しい人生を求めて、放浪の旅に出たのだ。出家ではなく…
-

連載11602回 歩くための技法 <1>
私たちは、ふだん何気なく歩いている。 歩き方を教わったわけでもないし、自分で工夫するわけでもない。 大部分の人は、ごく自然に、無意識に歩いているのだろうと思う。 べつにそれで不自由はなく…
-

連載11601回 『面白半分』という時代 <5>
(昨日のつづき) 『面白半分』みたいな雑誌が存在するということは、その社会が多様性に富んでいるということだ。余裕がないと一色になる。戦時中のこの国がそうだった。あの時代に『面白半分』などと称したら、…
-

連載11600回 『面白半分』という時代 <4>
(昨日のつづき) 『面白半分』の編集長をつとめて、私のやったことといえば『腰巻大賞』を作ったくらいだろう。 かねがね新刊のオビを厄介に思っていたのだ。だが編集者に「オビはつけないでくれませんか」…
-

連載11599回 「面白半分」という時代 <3>
(昨日のつづき) 西洋人のモノと日本人のモノのちがいを、<日本人のモノは構造的でカザリが多い>というのは、具体的にどういうことだろうか。 金子光晴さんの『随筆』ならぬ『随舌』は、とどまるところ…
-

連載11598回 「面白半分」という時代 <2>
(昨日のつづき) 『面白半分』誌の創刊1号と、廃刊臨終号を送ってくれたのは、私の郷里の八女市のMさんである。 Mさんは長年にわたって、いろいろと私に貴重な資料をみつけては送ってくださっていて、八…
-

連載11597回 「面白半分」という時代 <1>
むかし『面白半分』という雑誌があった。 「ハーフ・シリアスということだな」 と、吉行淳之介さんは言っていた。 面白さ一辺倒ではない。さりとて真面目全部でもない。中途半端を最初から打ち出した…
-

連載11596回 遅かれ早かれ散る桜 <5>
(昨日のつづき) 生きているだけで意味がある、とは、私が50年以上、言い続けてきていることだ。 「でも、生きてるだけじゃ――」 と、不満げな若い人からの反論も少くない。 「生きる意味、って…
-

連載11595回 遅かれ早かれ散る桜 <4>
(昨日のつづき) 私もときどき、夜、眠れないことがある。「明日は午前中から仕事だから、早く寝よう」とベッドに入るが、なかなか眠りが訪れてこない。 そんなとき、先に逝った仲間たちの顔を思い出し、…
-

連載11594回 遅かれ早かれ散る桜 <3>
(昨日のつづき) 坂本龍一さんが亡くなった。 <桜散る 昭和も遠くなりにけり> 坂本さんは大江健三郎さんとは別な意味で、知のリーダーの一人だった。なにか時代の扉がグルリと一回転したような感じ…
-

連載11593回 遅かれ早かれ散る桜 <2>
(昨日のつづき) 〽貴様と俺とは同期の桜 そんな歌を子供までがうたった時代があった。 〽咲いた花なら散るのは覚悟 見事散りましょ国のため と、続く。オレも中学生になったら、少年航空兵か予科…
-

連載11592回 遅かれ早かれ散る桜 <1>
先月からの喉の違和感がまだ消えない。消えないどころか、ますます抵抗が大きくなってくるようだ。 ひょっとしたら食道か喉頭のガンかも、という不安が頭をよぎる。それでも病院で診てもらおうとしないのは、…
-

連載11591回 ボケとトボケの間には <5>
(昨日のつづき) ボケもトボケも、現実からの離脱という点においては変りはない。 物ごとに正面から対峙しようとしない姿勢においても同質である。 ただ、ボケは自然の退行であり、トボケは意図的な…
-

連載11590回 ボケとトボケの間には <4>
(昨日のつづき) <三日見ぬ間の桜かな> という文句を、ずっと誤解していた。 咲いた桜も、3日もたつと散ってしまう。はかないものだ、と詠嘆する感じだろうと思っていたのだが、さにあらず。 …
-

連載11589回 ボケとトボケの間には <3>
(昨日のつづき) 規則正しい生活もアブない。 これは私がひそかに感じはじめていたことだ。 規則正しい生活は大事である。しかし、年がら年中、ずっと一分の狂いもなく暮す生活は問題だろう。 …
-

連載11588回 ボケとトボケの間には <2>
(昨日のつづき) 某出版社のベテラン編集者Q氏。 もう40年以上のつきあいだからQさんとはよばない。<Qちゃん>とよぶ。むこうも<イツキさん>だ。 定年退職して、今は嘱託。悠々と仕事を楽し…
-

連載11587回 ボケとトボケの間には <1>
<男と女のあいだには、深くて暗い河がある──> と野坂昭如はうたった。 知っていることを忘れてしまうことを、ボケるという。 知っているのに知らないふりをすることをトボケると言う。 一見…