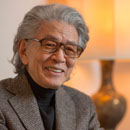五木寛之 流されゆく日々
-

連載11129回 もうひとりの親鸞 <2>
(昨日のつづき) 昨日の文章を読み返してみて、どうも今ひとつしっくりこない感じがした。 ここはやはり「である」調の偉そうな文体よりも、人に話しかける感じの喋り口調のほうがしっくりくるような気が…
-

連載11128回 もうひとりの親鸞 <1>
世界は矛盾だらけだ。私は10代の頃からずっとそう思ってきた。いまもその考えは変らない。人類は古代から現在まで戦争を続けてきたし、これからもそうだろう。 そんな世界に生きていくためには、励ましが必…
-

連載11127回 非・常民の地底を這う─「朝倉喬司芸能論集成」─ <4>
(前回のつづき) どこから読めばいいのか見当もつかないほど分厚い本の適当な部分を、エイと気合いを入れて開く。 とても最初から順番に読んでなどいられないカオスなのだ。開いて出会った文章が勝負であ…
-

連載11126回 非・常民の地底を這う─「朝倉喬司芸能論集成」─ <3>
(昨日のつづき) この膨大な論集の一冊を簡単に紹介することは難しい。 しかし、巻頭の『バナちゃんの唄――バナナ売りをめぐる娼婦やヤクザたち』に目を通しはじめると、文字通り巻をおくあたわずの状態…
-

連載11125回 非・常民の地底を這う─「朝倉喬司芸能論集成」─ <2>
(昨日のつづき) 私は若い頃、ロシア文学がやりたくて早稲田の露文科にはいったのだが、結局、朝倉喬司と同じように横に出た。(中退のこと) 在学中に影響を受けたのは、横田瑞穂、谷耕平、ブブノワ女史…
-

連載11124回 非・常民の地底を這う─「朝倉喬司芸能論集成」─ <1>
1000円以下の新書・文庫本が幅をきかせる当節、両手でも抱えるのに苦労する反時代的なヴォリュームの本が登場した。 「芸能の原郷 漂泊の幻郷」 と銘打った故・朝倉喬司の仕事の集成である。(「朝倉…
-

連載11123回 文壇ゴルフの思い出 <5>
(昨日のつづき) 数日前のこの欄で、名前のミスがあった。<独文学者の中野孝次さん>となっていたのは私の間違いで、正しくは<中野好夫>さんの話である。中野孝次さんは『清貧の思想』『ブリューゲルへの旅…
-

連載11122回 文壇ゴルフの思い出 <4>
(昨日のつづき) 当時の文壇ゴルフの話をするなら、大久保房男さんをおいてほかにいないだろう。私などが文壇の片隅からのぞいたこぼれ話を、知ったかぶりして書くのは、おこがましい限りではある。 とは…
-

連載11121回 文壇ゴルフの思い出 <3>
(昨日のつづき) マスターズを松山英樹選手が制して以後、ジャーナリズムでのゴルフ関連記事の扱いが急に大きくなったような感じがするのだが、どうだろうか。 今朝の新聞でも、バイデン大統領がゴルフを…
-

連載11120回 文壇ゴルフの思い出 <2>
(昨日のつづき) 文壇ゴルフのなかでも、ことに縁があったのは講談社だった。社としての催しのほかに青蕃会というグループがあって、『群像』編集長の大久保房男さんが教頭格でとりしきっていた会だ。 青…
-

連載11119回 文壇ゴルフの思い出 <1>
現金なものだ。松山英樹選手がマスターズで優勝したとたんに、若い人たちの間でゴルフがブームの観を呈しているという。 テレビ番組でも、いち早くその話題をとりあげていた。 若いOLや女子学生たちが…
-

連載11118回 コロナ下のマスターズ <5>
(昨日のつづき) 以前、このコラムで、 「家貧しゅうして孝子いず」 という格言を使ったが、あらためてそのことを痛感する今日この頃である。 今朝の日経新聞に目を通していたら、こんな文章が目…
-

連載11117回 コロナ下のマスターズ <4>
(昨日のつづき) これまで長いあいだ日本人選手はメジャーで勝てなかった。 「結局、ゴルフってのも向うさんのスポーツなんだよな。日本人は水泳とか柔道で勝つしかないんじゃないの」 などと誰もが諦…
-

連載11116回 コロナ下のマスターズ <3>
(昨日のつづき) 先ごろ世を去った三好徹は、麻雀の仲間であると同時に、ゴルフの同期生でもあった。 講談社の大久保さんといえば、泣く子も黙るもと『群像』の編集長で、同時に丹羽学校の教頭として有名…
-

連載11115回 コロナ下のマスターズ <2>
(昨日のつづき) この一年間、早寝早起きの生活が続いた。 夜は11時半頃ベッドにはいり、朝の7時半には目が覚める。 これまで60年あまりの深夜生活が、コロナの流行とともに一変したのだ。 …
-

連載11114回 コロナ下のマスターズ <1>
朝、起きてテレビをつけたら、オーガスタの3日目、松山英樹選手がトップになっている。 これで彼はマスターズは10度目ぐらいの挑戦だろうか。毎回、肩すかしをくらうのが例なので、あまり期待していなかっ…
-

連載11113回 話は人の為ならず <5>
(昨日のつづき) 徳川夢声は希代の話者だった。 もちろん天賦の才もあっただろう。しかし、それ以上に「話すこと」を研究し、鍛練した努力の人だったと思われる。 喋ることについて、彼は、 <自…
-

連載11112回 話は人の為ならず <4>
(昨日のつづき) ふと、このコラムの通しナンバーを見たら、今回(4月7日発売)で11111回となる。1万回以上の連載になろうとは、執筆開始のときにも想像していなかった。たぶん1、2年で本紙がツブれ…
-

連載11111回 話は人の為ならず <3>
(昨日のつづき) 三好徹さんが亡くなったことを新聞で知った。読売新聞の記事だが、他紙には出ていないのが不思議だった。彼は私より1つ年上の昭和6年の生れだが、麻雀仲間だったので「さん」はつけずに三好…
-

連載11110回 話は人の為ならず <2>
(昨日のつづき) ひとりで喋りまくるのも良くないが、逆にほとんど発言しないというのも問題だ、と夢声は言う。 いわく「黙り石となるなかれ」 先輩に遠慮するのは当然だが、はじめから終りまで石の…