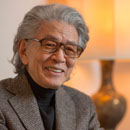五木寛之 流されゆく日々
-

連載10795回 ピンピン・ソロリの夢 <5>
(昨日のつづき) このところ様々な人の訃報に接することが多い。時代の回転扉がゆっくりと回っていくような実感がある。 私たち昭和ヒトケタ世代が去り終ると、その後には、いわゆる「団塊の世代」の大退…
-

連載10794回 ピンピン・ソロリの夢 <4>
(昨日のつづき) 昔、あるドクターが人生二回説をとなえて、話題になったことがあった。 20代の若いうちに、うんと年上の女性と結婚する。ある程度の経済力のあるキャリアウーマンが望ましい。 そ…
-

連載10793回 ピンピン・ソロリの夢 <3>
(昨日のつづき) かつて満州国や台湾では、阿片を利用して植民地経営の財政的土台とした。富裕層には阿片を、労働者たちにはモルヒネを使用させたのである。 古い中国や満州には、阿片窟と呼ばれる店があ…
-

連載10792回 ピンピン・ソロリの夢 <2>
(昨日のつづき) 「この世は苦の世界である」 仏教はそこにどう生きるかを教える道としてスタートした。 人生五十年といえども大変だ。まして百年生きるとなれば、想像を絶する。しかも成長期、安定期…
-

連載10791回 ピンピン・ソロリの夢 <1>
このところ老衰による死が激増しているらしい。 昔は死亡原因を「老衰」と書くのは医者としてはばかられる事だったという。もっともらしい死因、病名を無理してでもつけたのだろう。 しかし、老衰という…
-

連載10790回 回想の森をめぐって <5>
(昨日のつづき) いま私たちの世界は、ほとんど回想することを忘れているかのように思われる。 戦後七十余年、最近は戦前、戦中、戦後の記憶さえ回想されることが少い。 「そんなことはないんじゃない…
-

連載10789回 回想の森をめぐって <4>
(昨日のつづき) 回想にふけるというのは、イメージとは反対に、積極的な行為である。それは個人の歴史をふり返るだけではない。 私たちは常に一つの時代を生きてきた。自分の過去を思い返すことは、当然…
-

連載10788回 回想の森をめぐって <3>
(昨日のつづき) 未来は回想によって予見される。過去をふり返らない者に明日はない。 しかし、人は成長期には背後を見ようとはしないものだ。一直線に未来への夢を追い続ける。例外はあっても、それが普…
-

連載10787回 回想の森をめぐって <2>
(昨日のつづき) 最近よく聞く言葉にフレイルというのがある。高齢者の筋力や体力が落ちて、日常生活に支障をきたすほどに衰えが出てくることをいうらしい。 体力の衰えは自然の理である。しかし、少しで…
-

連載10786回 回想の森をめぐって <1>
最近、物忘れがひどくなってきた。ことに人の名前がなかなか思い出せない。先日も会話のなかで、アンジェイ・ワイダ監督の名前が出てこなくて苦労した。相手のジャーナリストが得意気に、 「アンジェイ・ワイダ…
-

連載10785回 夜ごとに変る波枕 <5>
(昨日のつづき) これまでにも繰り返し書いてきたことだが、「面授」という言葉がある。仏教の世界などでよく使われてきた単語だ。 「面授」とは、文字通り対面して教えを受けること。肉声で、表情や身ぶり…
-

連載10784回 夜ごとに変る波枕 <4>
(昨日のつづき) 対談というからには、どこかに対立も必要である。最初から最後まで和気藹藹というわけにはいかない。 とはいうものの、いきなり相手の意見に反論して、双方が不愉快になるのも困る。その…
-

連載10783回 夜ごとに変る波枕 <3>
(昨日のつづき) 対談というのは、まとめが命だ。どんなにその場で活気のある対談であっても、活字にまとめた時点で駄目になってしまう事もある。 向かいあって話をしているとき、こちらが言葉を発しなく…
-

連載10782回 夜ごとに変る波枕 <2>
(昨日のつづき) 先週は立て続けに3つの対談をした。又吉直樹さん、塩野七生さん、そして昨日の文章で触れた中西進先生である。 昔は年長者と対談をすることが多かったが、80歳を過ぎてからはほとんど…
-

連載10781回 夜ごとに変る波枕 <1>
昨日、中西進先生と対談をさせて頂いた。いまや時の人どころではない、国民的注目の的となった万葉学者である。 私はこれまで大先輩作家に対しても先生と呼んだことはなかった。不遜といえば不遜かもしれない…
-

連載10780回 金のかからぬ養生法 <5>
(昨日のつづき) 養生法と健康法はちがう、と最初に書いた。たとえばジムに行って体を鍛えるのは、健康法の一種である。肥満を解消し、筋肉をつけるメソッドだ。 それは人生の前半期の人々には大いに有効…
-

連載10779回 金のかからぬ養生法 <4>
(昨日のつづき) 最近の健康情報の氾濫ぶりはすさまじいものがある。あらゆるメディアに健康に関する情報がとりあげられて、それがそれなりに大きな反響があるらしい。 健康本と称される出版物も次々に刊…
-

連載10778回 金のかからぬ養生法 <3>
(昨日のつづき) 養生法と健康法はちがう。 健康法を説く人は、本人がまず健康でなくてはならない。病人が健康法を語ったとしても、誰も耳を傾けないだろう。 養生とは、弱い体をなんとか維持するた…
-

連載10777回 金のかからぬ養生法 <2>
(昨日のつづき) 深い呼吸をすることが大事だ、とわかっていても、なかなか人は実行しないものだ。 努力をする、ということはむずかしい。世の中には努力家というタイプの人がいる。生まれつき努力が好き…
-

連載10776回 金のかからぬ養生法 <1>
物心ついたときから、常識に逆らうようなことばかりやってきた。 小学生の頃、「心頭を滅却すれば火もまた涼し」という文句に出会った。なるほど、と思って、ローソクの灯に指をかざして火傷をしたことがある…