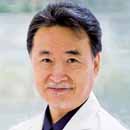正解のリハビリ、最善の介護
-

介護状態を防ぐ「酒向メソッド」の高齢者トレーニングとは?
高齢者で、筋肉、骨、脳神経をきっちりと鍛え続けている場合、認知症になる方はあまりおられません。しかし、鍛えることをやめてしまうと、認知症に進行する方がいらっしゃいます。つまり、「脳筋相関」があるので…
-

介助状態にならないための「酒向メソッド」とは?
50歳以上の年齢を迎えると、体の変化に気づき始めます。そして、その後は10歳ごとに、筋肉、骨、脳神経が徐々に低下していきます。60歳を越えると心肺機能も低下してくるので、特に体力の低下を実感します。…
-

「高次脳機能障害」と「認知症」…症状がほぼ同じなのに、治療法がまったく異なる理由
「高次脳機能障害」と「認知症」で現れる症状は実はどちらもほぼ同じです。しかし、その病態は異なるので、症状の変化がまったく異なります。 このため、治療法もまったく変わります。 共通する症…
-

認知症の内服治療のポイントは? 重症度や症状によって有効な薬は変わる
認知症の治療は、「環境調整」「関わり方(接し方)」「内服治療」の3本柱です。環境調整と関わり方のために“正解のリハビリ”があり、それによって“最善の介護”が継続できると考えます。 では、認知…
-

認知症で問題行動を起こす患者にはどんな対応をするのか
「ビックリしました。まるで別人です……こんなに良くなるんですね。表情がまったく変わりました。本当にありがとうございます。うれしいです」 85歳の女性が当院に入院されてから1週間後、ご家族からこ…
-

認知症の家族は自宅で介護したほうがいいのか?
ねりま健育会病院に併設されている介護老人保健施設(老健)は、在宅復帰とアフターケアに力を入れた超強化型老健です。認知症の患者さんが入所された場合、定められた3カ月の入所期間で、軽症、中等症、重症、そ…
-

認知症の「重症リハ」はどのように取り組めばいいのか
認知症はサプリやリハビリで治りますといった誇大広告をよく見かけます。認知症は加齢とともに進行しますので、治る病気ではありません。ですから、本人と家族が困る症状をどうやって和らげてあげることができるの…
-

アルツハイマー型認知症のリハビリで注意すべきポイントは?
認知症を発症後のリハビリは、病気の種類と特徴を把握したうえでアプローチすることが大切になります。 今回はアルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症について取り上げます。 アルツハイマ…
-

前頭側頭型認知症のリハビリではスケジュールが重要なのはなぜか?
認知症の中等症リハでは、施設でも自宅でも、1日単位のスケジュールと1週間単位のスケジュールをきちんと決めることが大切だと前回お話ししました。決まった時間にどこに行くのか、何をするのかといったスケジュ…
-

認知症の中等症リハではなぜ「楽しんでできること」を探すのが重要なのか
認知症を発症後、軽症の段階から中等症に進行した患者さんに対し、できるだけ生活が困らないようにするために実施するリハビリが「中等症リハ」です。 中等症になると、記憶障害が加速して新しい出来事が…
-

認知症の「軽症リハ」で、昼夜逆転の生活リズムを戻すこと重要なのはなぜか
認知症を発症後、軽症の段階で介入して、できる限り進行を遅らせ、“できる能力”を向上させる認知機能向上リハビリが「軽症リハ」です。 私が院長を務める、ねりま健育会病院に設置している「介護老人保…
-

認知症の「軽症リハ」では具体的にどんなことを行うのか
当院で実施している認知症リハビリのうち、今回は「軽症リハ」についてお話しします。 認知症発症後、進行を遅らせて“できる能力”を向上させるためのリハビリです。 認知症には進行度が定めら…
-

認知症の予防リハビリで“頭”を使った訓練は有効なのか?
ねりま健育会病院の「介護老人保健施設(老健)」では、認知症ではなくても高齢者の「認知機能向上リハビリ」を実施しています。前回は、認知症の発症を遅らせるために取り組む①「予防リハ」のうち、筋力トレーニ…
-

認知症リハビリでは具体的にどんなことを行うのか?
私が院長を務めるねりま健育会病院は、急性期治療後に病気やケガで後遺症が残ってしまった患者さんが対象になる「回復期リハビリ病院」と、慢性的な疾患を抱えていたり全身状態が衰えている要介護の高齢者を対象と…
-

いいリハビリ病院を見分けるには看護師が重要なのはなぜか
「先生、私のおじいちゃんは脳卒中で亡くなったんです。その時、私は中学生で、どんどん弱っていくおじいちゃんに何もできなくて、つらくて……。それで看護師になったんです。どう頑張ったら、おじいちゃんを良くし…
-

攻めのリハビリで「評価」が重要なのはなぜか?
攻めのリハビリで人間力の回復を目指す際は、患者が現在どのような状態なのかを把握する「評価」が大切だと前回お話ししました。本人、家族、治療チームの全員が共有すべき最低限の評価は7項目あり、前回は触れら…
-

機能や能力が低下したときは何を「評価」すればいいのか?
「攻めのリハビリ」を実践して人間力の回復を進めるためには、患者が現在どのような状態なのかを把握する「評価」が欠かせません。 では、脳卒中や脳外傷などの脳血管疾患、運動器疾患、廃用症候群、そして…
-

「攻めのリハビリ」を実践するために“いい医者連携”が必要なのはなぜか
「攻めのリハビリ医療」を進めるには、リハビリ医が患者さんの全身を管理することが欠かせません。それぞれの患者さんに対し、現在の症状を生じさせている病態を把握したうえ、回復期病院に入院する理由となった原疾…
-

運動器疾患と廃用症候群を予防するためにはどんな対策が必要なのか
リハビリ医が「攻めのリハビリ」を実践するには、患者さんの全身管理を行う能力が欠かせません。中でも、再発を予防する医療に関する知識と対応力が求められます。 前回お話ししたように、回復期リハビリ…
-

リハビリ医にとって絶対に欠かせない能力はなにか?
リハビリ医が「攻めのリハビリ医療」を進めるには、患者の全身管理を行う能力が必須です。特に高齢者の全身管理に関する知識が必要で、すべての病気に対して集中治療室治療と手術以外は対応できる力が求められます…