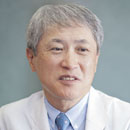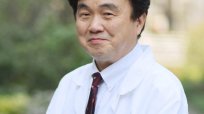理想の去り際は「惜しまれつつ、されど潔く」
私が診ている患者さんの中に、明治大学の野球部で星野さんと一緒にプレーしていた方がいらっしゃいます。星野さんが亡くなったとの知らせを受けたとき、「ずっと親しくしていたのに、自分には何も言ってくれなかった」とひどく落ち込まれていました。「最後に会ったときにまたメシでも食いに行こうと約束して別れたのに、それも果たせなかった……」と、まわりから見ても無気力な状態になってしまったのです。
自分が不治の病に侵されたとき、周囲には知られたくないと考える人もいます。肉親だったり、親友だったり、近しい人が自分が病気だと知ったとき、自分のことのように気遣ってくれる。そうした人たちに病気であることを伝えたら、いろいろと煩わせてしまうことになるし、これまでとは関係性が変わってしまう。それを嫌がる人がいるのです。
おそらく、星野さんも男としてそうした気持ちがあったのではないでしょうか。残された人が無気力になってしまうのはその気持ちに報いていないのではないか。落ち込んでしまった患者さんに、私はそう言葉をかけました。死を迎えることによって肉体は滅びますが、魂も永遠の眠りにつくか、そこから新たな覚醒(評価)を得るかは残された人たちの思い一つです。生き残るということはその責任を果たすことに他なりません。
死に対する考え方は人それぞれで、正解も不正解もありません。惜しまれつつ去る、されど去り際は潔い。私にとっては、それが理想の“死にざま”だと思っています。