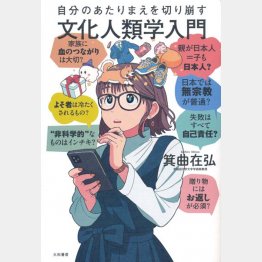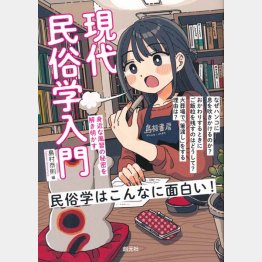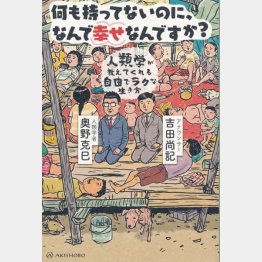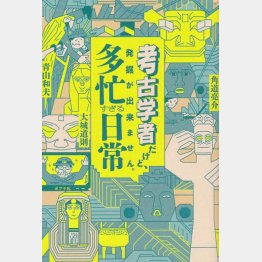多様性が日常に風穴をあける 人類学・民俗学の本特集
「自分のあたりまえを切り崩す文化人類学入門」箕曲在弘著
世界にはさまざまな民族が存在し、「ええっ?」と思うような文化、風習がある。それを研究するのが人類学や民俗学だ。そういう多様性を受け入れることが我々の発想や価値観に風穴をあけてくれるかもしれない。
◇ ◇ ◇
「自分のあたりまえを切り崩す文化人類学入門」箕曲在弘著
「日本人」には「国民としての日本人」と「民族としての日本人」がいるが、では「民族」とは何か。日本国籍をもっているかどうかで決まるのではない。外国にルーツをもつ人も日本国籍を取得することはできる。逆にアメリカ国籍やイギリス国籍でも、ノーベル賞受賞者が「日本人」としてメディアで取り上げられることもある。
同じ文化や生活様式を共有しているという見方もあるが、宗教を含めかなりあいまいである。
「日本人」の定義として「血筋」を挙げる人が多い。「日本人」の両親から生まれたから日本人なのだということである。「族」には、同じ祖先から分かれた血統のものという意味があるからだ。
文化人類学者が「日本人とは何か」の定義から始める入門書。
(大和書房 1980円)
「現代民俗学入門」島村恭則編
「現代民俗学入門」島村恭則編
「中元」とは中国の暦で旧暦7月15日のこと、「歳暮」とは年末のことである。この時期に贈られる贈答品が「お中元」「お歳暮」だ。中元は「夏から秋へ」歳暮は「冬から春へ」という季節の変わり目で、魂の更新が行われるとされていた。
季節の進行の中で人の魂は衰えるので、一定の時期にパワーアップしなければならない。パワーのある子供や目下の者が、パワーの衰えた親や目上の者に自分の魂を分割して与えることで、受け取った側は魂をパワーアップできるのだ。(「お中元、お歳暮は何のために贈るのか?」)
ほかに、運動会で行われる「綱引き」は元来はカミの意思を占う「年占(としうら)」だった、「初夢」とは元日の夜でなく2日の夜に見る夢をいうのはなぜかなど、私たちの身近な風習に隠された意外な意味を紹介する。
(創元社 1980円)
「何も持ってないのに、なんで幸せなんですか?」奥野克巳、吉田尚記著
「何も持ってないのに、なんで幸せなんですか?」奥野克巳、吉田尚記著
文化人類学者の奥野はボルネオのジャングルに住む狩猟民「プナン」の暮らしを取材した。上下水道はなく、トイレは野外でする。個室もなく、カレンダーもない。「幸せ」という言葉はないが、いつも笑顔と平和な空気はある。彼らの考え方を知ることができれば我々も幸せになれるのではないか。
プナンは一日中、寝転がって世間話をしている。東プナンと西プナンがあって、東プナンは林道封鎖などの抵抗運動をしているが、西プナンは関わっていない。プナンには個人所有の感覚がなく、奥野が持ち込んだ本や食料が留守の間に持ち去られたことがあった。それは誰かの所有物ではなく、「そこにある」のだ。彼らが「所有」を否定しているということが徐々に分かってきた。
人類学者が出合った自由で楽な生き方をリポート。
(亜紀書房 1980円)
「考古学者だけど、発掘が出来ません。多忙すぎる日常」青山和夫、大城道則、角道亮介著
「考古学者だけど、発掘が出来ません。多忙すぎる日常」青山和夫、大城道則、角道亮介著
大城は大学入学後すぐ、古代文字ヒエログリフを学ぼうと研究者を訪ねたが、大学院生でなければ教えられないと断られた。とりあえず古代エジプト研究会に入会したおかげで、教授に教えてもらうことができた。ヒエログリフが読めていい論文が書ければ大学や博物館などの研究者になれると思ったのに、そもそも公募や募集がなかった。教授に「シリアには人類文明のすべてが詰まっている」と勧められて長期の休暇にシリアに行くことに。
その後、大学の教員としてサハラ砂漠などへ行くのだが、そこはバスタブもシャワーもなく、自分の体内から出したものはビニール袋に入れて持ち帰るという世界だった。(「エジプト考古学者の多忙すぎる日常」)
ほかに、石器の分析に追われて発掘するヒマがないマヤ文明の研究者らの日常を紹介する。
(ポプラ社 1760円)