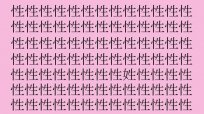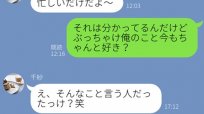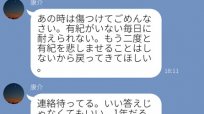東京・国立の景観美と街の財産 地元在住43年の写真家がたどる…新築マンション解体騒動で話題
街を見つけてきた87歳のマスターは
市で最古参のスタンドバー「レッドトップ」のオーナー兼マスターの岡本貞雄さん(87歳)が言う。
「当時は米兵に酒を提供していただけでしたが、『風紀を乱す』と偏見を受け、ずいぶんいじめられました」
駅から歩いて1分、まさに富士見通りの入り口近くにある。木製の扉を開けると、マリリン・モンローの写真やアメリカ20世紀絵画の巨匠エドワード・ホッパーの名画(複製)などが飾られている。正統派スタイルを続けて今年65周年を迎えた。市料飲店組合会長も務めた街の生き証人だ。岡本さんに街の移り変わりを聞いた。
50年代はスタンドバーの最盛期。ニッカウヰスキーを扱う「ニッカバー」として59年に開業したという。
「当時は1杯50円のハイボールが人気でした。深夜0時を過ぎると米兵がやって来て、アメリカの禁酒法時代に闇で飲まれたカナディアンウイスキーを好んで飲んでいました。大学通りはまだ砂利道でね。近所にあった店は、喫茶店の『ロージナ茶房』と『邪宗門』(2008年に閉店)、ウチの3軒だけでした」
駅前の屋台で一杯飲んでから流れてくるハシゴ酒の人たちでにぎわったそうだが、東京五輪(64年)で風向きが変わる。営業時間が24時までに規制され、スタンドバーブームはあっけなく終わり、多くがスナックへと業態を変えたという。
■文化人も住民を大事にした「語る場所」
店が苦境を乗り越え、生き残ったのは?
「お客さまの質が変わらなかったから」
常連客たちが「語る場所」を守ったことが大きいという。
65年には公団団地が建設されて人口が増加、67年に国立は市になる。その団地に住んでいた漫画家の滝田ゆうも常連のひとり。滝田の特徴ある絵が店のコースターとマッチ箱を飾ったのはこの頃で、店には大手企業の社長や大学教授、元学長ら職業の垣根を越えて人が集まった。4コマ漫画で有名なサトウサンペイ、編集者の嵐山光三郎もその面々だという。
70年代にはバーボンが流行。「ジムビーム、アーリータイムズ、ハーパーがよく出ましたね」と笑顔を見せる。街には純喫茶、居酒屋、バーなど地元に会話ができる場所がたくさんあって、客たちはそういう店を渡り歩いて交流した。陽気な時代だったそうだ。
80年代後半、国立に再び逆風が吹く。飲食チェーンが続々と進出した一方、経営者の高齢化も伴って老舗店が減少していった。街の歴史を知り、街を愛していた戦前・戦中世代がいつのまにか消えていったという。
マンション解体の話題について改めて尋ねると、「実は『またか』という思いがあって」と前置きをして、静かに語り始めた。
「この街の大学に入り、街が気に入って家を建て店の常連になっている方も少なくありません。人も学校も企業もこの街をつくってきた仲間です。右だ左だとか、開発か保全かという対立ではなく、もっとうまく話し合ってほしかったですね」
国立市は89年、商業地の建築物規制を緩和すると、高層マンション問題が相次ぐ。90年代に入って東京海上火災が大学通りの一角にある社屋建て替えを計画。敷地の樹木を切ろうとして、樹木保全を望む人たちと軋轢が生まれた。東京海上は用地を売却し、国立を去る。同社の撤退は雇用や飲食店などには逆風に。「もっとうまくやれよ!」という地元民の声を当時私も聞いた。
その用地は大手ディベロッパーに渡る。それが、今回のマンション問題とは別の「国立マンション訴訟」へと発展。詳細は省くが、建設反対派は敗訴する事態になった。
リアルに会話ができる場も街から消え、景観を守る運動をする人たち、運動はしないが保全を望む人たち、雇用者や飲食店。それらがつながらなくなっていった。
当時は西武グループの不祥事も続発。街の基礎をつくった堤一族へのリスペクトは口に出しづらくなり、街の歴史を振り返る機会も減った。