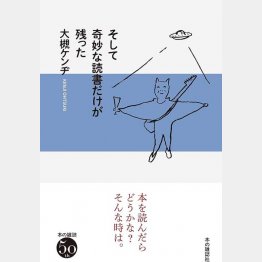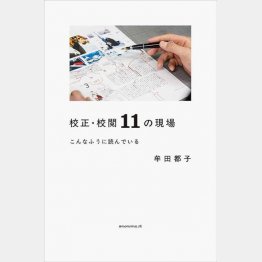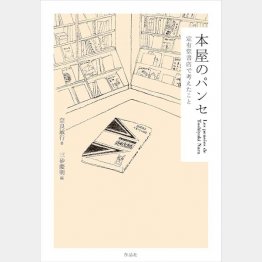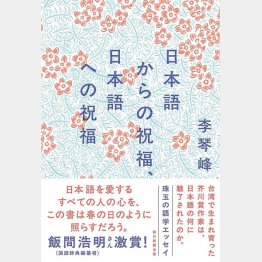未知の世界へ!書籍にまつわる本特集
「そして奇妙な読書だけが残った」大槻ケンヂ著
普段の読書は、どうしても好きなジャンルに偏りがちなもの。しかし、それだけではもったいない。そこで、今週は未知なるジャンルへの手掛かりとなる本や、広大で奥深い本の世界へ導いてくれる本、そして日本語にまつわる本を集めてみた。
◇ ◇ ◇
「そして奇妙な読書だけが残った」大槻ケンヂ著
ロックミュージシャンによる読書エッセー集。
高野秀行氏の自伝的小説「ワセダ三畳青春記」を読書中、著者はあるエピソードに登場する男が「リアル犬神明」だと気づく。リアル氏は、平井和正氏の小説の主人公・犬神明について、これは自分のことだと名乗り出た男で、1986年には「SFアドベンチャー」誌で、平井氏と対談までしている。さらに、そのリアル氏こと塩野智康氏が登場するさまざまな書籍などにも触れながら、なぜ今、リアル氏について考察するのか、高校時代までさかのぼり私的体験を明かす。
以降、古書店で見つけたわずか8ページの雑誌「ギリギリマガジン」にまつわる怪しげな思い出や、バンド本として読んでいた「中西俊夫自伝」に突如出現する宇宙人との遭遇エピソード、サイエンスフィクションならぬストリートファイト=SF本「護道の完成 自他を護る実戦武道」(廣木道心著)など。ジャンルを横断して語り尽くす。
(本の雑誌社 1870円)
「校正・校閲11の現場」牟田都子著
「校正・校閲11の現場」牟田都子著
本や雑誌はもとより、字幕や商品パッケージ、ウェブサイトまで、日常にあふれるありとあらゆる言葉を、世に出る前にあらかじめ目を通し、誤りがないか確かめ、不足を補うのが校正者の仕事だ。
本書は、自身もフリーの校正者である著者が、同業者たちはどのような気持ちで、どのように仕事をしているのかをたずねて歩くインタビュー集。
講談社校閲部の大津留久美子さんは、総合出版社ゆえに雑誌や書籍などすべてのジャンルを経験し、現在はコミックの校閲を担当。苦手なのは文芸書で、文字遣いも言葉遣いもすべての表現が著者独自のものであると考えると、校正が何をしたらいいのか悩むという。そしてコミックの場合は、言葉の勢いを殺さないことを最優先にしているなど、失敗談も含め語る。
以降、レシピや辞書、法律書、地図など、裏方として日本語を守り、支える11ジャンルそれぞれの校正・校閲者の話から、仕事の実際と魅力を聞き出す。
(アノニマ・スタジオ 2200円)
「本屋のパンセ」奈良敏行著、三砂慶明編
「本屋のパンセ」奈良敏行著、三砂慶明編
著者の奈良氏は、鳥取県鳥取市で1980年に創業した町の本屋、定有堂書店の店主。同店は、独自の選書と取り組みが全国各地の書店員に注目され、2023年に閉店するまで「書店員の聖地」とも呼ばれた。本書は、氏が店で発行していたミニコミ誌、そしてウェブサイトに場所を移して書き続けているエッセーを編んだ一冊。
店は若桜街道と袋川が交わる橋の北詰めにあり、川の土手には店側だけ桜並木が続く。桜が満開のある日、知人に誘われ、対岸から眺めると、いつもと違った風景が見える。
同じく対岸にある店の常連のお勧めの喫茶店「森の生活者」から川を眺めているうちに、思いはソローが過ごした「ウォールデン池」へと飛ぶ。
読者であることの体験だけで本屋を始めたという奈良氏が、本を届けるという前提のもとに読んでいた読書から、再び一読者に戻るまで。万巻の書を読みながら、店で出会った人々や本を手に深めた思索の一端をつづる。
(作品社 2420円)
「日本語からの祝福、日本語への祝福」李琴峰著
「日本語からの祝福、日本語への祝福」李琴峰著
日本語を母語としない作家として2人目の芥川賞作家となった著者の語学をめぐるエッセー集。
台湾の農村で育ち、周囲に日本語ができる人はおらず、日本語を選び、学習したのは、100%自分の意思だったという。
アニメや漫画によって幼い頃から日本文化に親しんできた著者は、ゲームに登場するカタカナやひらがなの文字の形の美しさに心をひかれる。そして、中学2年から本気で日本語を学び始めた。きっかけはなく、単なる気まぐれだったが、ひらがなとカタカナを書いているときは、自分にしか分からない暗号をつづっているような気持ちになった。独学でまずはひらがなを、カタカナはアニメソングを歌うことで学んだという。
ひょんなことから日本語にひかれ、日本語に恋をし、日本語と戯れ、時に挫折もしながら次第に身につけていく。やがて海を渡り、日本語の紡ぎ手となるまでを振り返り、日本語への思いをつづる。
(朝日新聞出版 1980円)