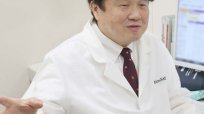(6)心電図が測れるスマートウオッチの仕組みと分かること
心電図が測れるスマートウオッチは、血圧と同じく世間の注目を集めています。しかし中身はあまり理解されていないようです。
仕組みですが、本体の裏面に電極センサーが1個ついています。電極が手首の皮膚に密着するようにし、もう片方の手の指で本体の横に付いているボタンに触れると、心電図の測定開始です。そのまま静かに30秒ほど待ちます。途中で動いたりすると、正確に測れません。結果はスマホアプリに送られて、AIや独自アルゴリズムによる判定が表示されます。
病院や健診の心電図検査は「12誘導」といって、胸に6個、両手首・両足首に各1個、合計10個の電極を取り付けて行います。電極は10個でも、12種類の波形が測れるので、こう呼ばれているのです。
対するウオッチは電極が1個だけなので、ズバリ「1誘導心電図」と呼ばれています。「12対1」ですから、ウオッチで判別できる病気は、当然ながらかなり限られています。たとえば、急性心筋梗塞や狭心症は分かりません。心不全や心肥大などにも無効です。つまりウオッチでは、メジャーな心臓病はほとんど分からないということです。