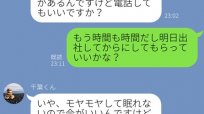デビュー作「みどりいせき」で文学界を騒然とさせた大田ステファニー歓人さんの素顔
「時間を奪える」から小説に
──卒業後は、映像編集や舞台照明の仕事を経て、営業職に。
その合間の時期にもいろいろバイトとかもしてましたね。すぐに金をくれる引っ越しとか荷揚げ、足場、解体。いろんな職に触れるのは、社会が人で成り立ってることを働いてる人間の側から感じられるいい経験でした。クリエーティブな職種だと仕事自体が楽しくなって、執筆がおろそかになる。肉体労働だと体を動かす喜びはあるけど、帰って書く体力がない。普通の仕事だと興味が湧かない。小説が書けるまでの腰掛けだって割り切って、金を稼ぐために適当に働くのも同僚に申し訳ない気持ちでした。
──面白みを感じられない仕事に励む傍ら、1作目を書いて群像新人文学賞に応募するも落選。ゴミ収集業に転職して、書き上げたのが2作目の「みどりいせき」です。不登校気味の高校生の主人公「僕」が、少年野球でバッテリーを組んでいた1つ年下の「春」と再会し、ドラッグ売りに足を突っ込んでいく。なぜ、ウィード(大麻)を題材に取り上げたのですか。
その構想が真っ先にあったわけじゃなく、学校や普通のバイト先、家族など高校生世代が入っているコミュニティーとは違うところに、自分たちだけでイチから共同体をつくっていく子どもを描こうってのが最初にあったんです。彼らの経済的な自立を描きたかったんですが、雇われの身だと、雇用主との権力勾配ができてインディペンデントを貫けない。どう働かせるかを考えた時に詐欺なんかも考えたんですけど、ちょっとビジネスっぽくなるというか。頭の良い高校生起業家みたいなノリはしょうもなかったんで、イリーガルな題材にしようと思ってウィードに行き着いたんです。
──なるほど。
高校生がウィードを手押し(直接取引)するという下敷きにすれば、社会があらかじめつくった規範とは離れた自分たちのルールに基づいて、間違っていたとしても信じて突き進む彼らなりのコミュニティーのあり方を相対化できる。法律や思想、経済的な面で彼らが「自立」できるし、ウィードは題材としての深みがあると思ったんです。合法な国がある一方、日本では所持していたら高校生だろうと、どこかのアメフト部だろうと、ニュースとして消費されて社会的に抹殺される。戦後に大麻取締法が制定されてから約80年の時を経て、青春を謳歌している高校生がウィードを再解釈するみたいな、そんな想像力をかき立てる題材としてハマりましたね。
──ウィードでキマっている表現の細やかさも際立っていました。
映画や音楽のPVなどに頻繁に出てくるから、情報を蓄積しつつ、しぐさや習慣などは最終的に取材で補完しました。不確かな描き方をすると良くも悪くも偏見の助長に加担しちゃうので、なるべく正確に実相を描く気持ちがありました。使ったら気持ちよくなるとか、体に合わないとか、判断は保留して、フラットに描こうと。この作品を読んだ人が、それぞれの感想で捉えればいいやって感じでした。
──今後の構想は?
他人と接する時、自分自身を守るために、相手と壁をつくることが誰でもあると思うんですが、ちょっと過剰なんじゃないかって。この過剰さは学校教育が影響していると思う。たまたま近所に住んでいた子どもが同じ教室にすし詰めにされて、仲良くさせられる。だから協調性がないと見なされないようにしたり、他人と違わないようにしたり、自分の手触りで素直に相手を理解することを無意識的に恐れちゃう。壁のつくり方だけうまくなって、本質的な心のつながりが分からなくなる。つながり方に明確な答えがあるわけではないけど、これから書く作品も、人と人とのつながりを自分なりに描写することに変わりはないです。
──日本の家庭や学校教育ではしばしば「他人に迷惑をかけるな」と教わりますね。
インドみたいに民族や宗教に多様性のある国って日本の教育と方向性が全然違うという話を聞いたことがあって、「生きていたら人に迷惑をかけるのは当たり前だから、お互いさま」みたいな。人口が多いから至った境地なのかもしれないけど、東京だって密度が高いんだから同じ。みんな迷惑。だったら迷惑前提で生きた方がいいんじゃないのって思います。自分の迷惑も他人の迷惑も許す。要はラブです。これから書きたい作品は全部ラブですね。
(聞き手=高月太樹/日刊ゲンダイ)
▽大田ステファニー歓人(おおた・すてふぁにー・かんと)1995年、東京都生まれ。日本映画大卒。