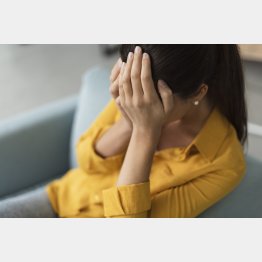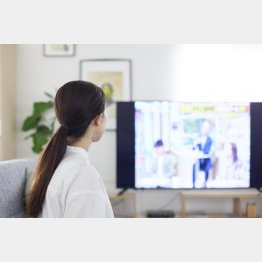お互いの「子どもの共通点」に愕然。平凡になったのは元彼と私、どっち?【新川崎の女・鈴木 真央41歳 #3】
【新川崎の女・鈴木 真央41歳 #3】
【何者でもない、惑う女たちー小説ー】
新川崎の大規模マンションに暮らす真央。「量産型主婦」を自覚しているが、かつての真央はバリバリの個性派女子だった。そこでかつての想い人に会ってしまう。同じ趣味やセンスを持っていた彼もまた、普通の中年パパに変貌していて…。【前回はこちら】【初回はこちら】
◇ ◇ ◇
「あああああああ、もう!」
キッチンの掃除をしながら、真央は突然大声で叫んだ。
夕食を終え、リビングのソファでくつろいでいた凛と文敏は、何事かとビクッと肩を震わせる。
「…どうしたの?」
「あ、いや、コンロについたコゲがどうしても落ちなくて」
言い訳したが、全くの嘘。夕方、キッズルームで銀二に投げかけられた言葉がふとよみがえり、突発的に爆発してしまったのだ。
『真央はずいぶん落ち着いたよね』
まるで二度目の失恋をした気分だ
だけど、それはこちら側のセリフだった。銀二の方が容貌も、雰囲気も、会話の中身も、何もかも変貌していたのだから。
強いて言えば礼音くんから、多少の彼らしさを感じるくらい。今どき珍しい五厘刈り。孤高の存在だった彼のマインドの片鱗を見た。凛も前髪ぱっつんおかっぱ頭だから、他人(ひと)のことは言えないが…。
――あの時、「あんたもね」と言い返せばよかった。
くすぶる感情を解消すべく、コンロのこすり洗いに没頭する。ずっと汚れを放置し、こびりついたコゲはなかなか取れない。
まるで、二度目の失恋をした気分だった。
空虚な気持ちを押し殺そうと、心を無にし、真央は必死で手を動かす。その甲斐あって、しばらくすると輝きを帯びてきた。
嬉しいのに、なぜか寂しさが吹き込む。
「…」
真央は、思い知る。
勝手に自分の中に『あの頃の銀二』を飼っていたのだということを。
彼はずっとあの街で、退廃とカルチャーに溺れながら汚れたままでいてほしかった。
――銀二は、あの頃のわたしの拠り所だったんだ…。
趣味は真逆だけど、優しい夫に惹かれた
喪失感は、自然とため息となって吐き出される。するとその異変に文敏が気づき、顔を覗きこんできた。
「ママ大丈夫? さっきから変だよ。疲れているんじゃない?」
掃除を変わってくれるという。優しい夫に素直に甘えることにした。
真央と夫・文敏は、就職して間もない頃、当時勤めていた会社の同僚が開いてくれたバーベキュー大会で知り合った。
同い年で車が趣味の彼。嗜好は真逆だったけど、銀二と真逆の誠実な性格に惹かれた。そして、ドライブデートでじわじわと親交を深めた。
彼の子どもと名前に「共通点」がある?
ドライブのBGMは彼の友人が編集してくれたというJ-POPヒット曲集。どれも真央の脇を通り抜けていたものばかりだったが、彼の趣味に合わせるように、あゆのSEASONSを慌てて覚えた。そして30歳の時に結婚…。
その頃を思い浮かべながら、ソファの上でスマホを眺めていると、学生時代の仲間で銀二との共通の友人・賢雄からLINEが届いた。
『おっつう~』
川崎で親の代から続く居酒屋を経営している賢雄とは、今でもたまに彼の店で顔をあわせる。映画マニアだが、仕事柄どこか軽さのある陽気な男だ。
タイミングからして、銀二がこの再会をLINEか何かで告げたのだろう。
真央は重たい気持ちで既読をつける。適当なスタンプで返信をするつもりだった。しかし、その内容に真央の目がとまった。
『真央の子どもの名前、リンとタケシって本当? 銀二の子供もレオンなんだろ!? やべぇな』
やべぇな、とは。なにがいけないのか。
答えを探る中で、しばらくしてやっとその理由にたどり着いた。
銀二が投げかけた「本当の」言葉の意味
なぜ気づかなかったのだろう、と真央は再び、奇声を発したくなる。
“武”と“凛”の名は、昔好きだった映画『恋する惑星』に出てくる俳優さんからとった。
金城武と、ブリジット・リン。学生時代から子どもができたらセットで付けたいと温めていた名前だった。親戚や夫には適当に由来をこじつけ、納得してもらった。
――まさか、レオンくんも…?
武と凛の名前を出したときの反応からして、銀二の息子も、あの映画に由来しているにちがいない。
適当にあしらっただけでなく、その意味にさえも気づかなかった。
変わったと言われても仕方ない。
いや、もう変わってしまっているのだ。身も心も、すべて。
時の流れに従っていれば人間が変わるのは必然だ。社会性を身に着けて、服装や言動が成長するのもあたりまえのこと。
だけど自分だけは、どんなに見た目は変わっても、芯は変わらないと思っていた。変わりたくなかった。センスも志向も考え方も、「ちょっと変わり者」を自負していた昔のままであるはずだと。
そんな、平凡な一般人になりきれない自分も好きだった。
でも――。
浜崎あゆみの歌詞を噛みしめる
「掃除、終わったよ。武を呼んで風呂入ってくるね」
「うん、ありがとう」
武と入れ替わりに文敏が24時間保温のシステムバスへ向かう。
人造大理石のキッチン天板、夫のおかげでピカピカになったビルトインコンロを見つめる。何もかもが恵まれた暮らしやすい環境、住居。ありふれた幸せがここにあることを実感する。
絵本を読みながらいつのまにか眠ってしまった凛に毛布をかけ、テレビ画面に目をやると、平成の懐メロ特集がやっていた。
浜崎あゆみのSEASONSが流れている。口ずさみながら歌詞を噛みしめる。
真央は、いい歌だと素直に実感した。何回もカラオケで歌っていたはずなのに、はじめて気づいたことだった。
『真央はずいぶん落ち着いたよね』
銀二の言葉を反芻する。口調に落胆が込められていた。彼もまた、あの時のままの真央を心の中でずっと飼っていたのかもしれない。
――別にいいよね、平凡になるのも。
バンドTシャツに彼も気づいているはず
数日後。天気のいい秋の昼下がり。棟に囲まれた円形広場のベンチ。
幼稚園バスのお迎えの時間まで、色づきはじめた並木道に時の移ろいを感じながら真央はその美しさにふける。落ち葉に染まる鮮やかな街路、枯葉を脱いだ木々の趣、その先の季節の変化に想像を膨らませる。
「おう、どうも」
誰かの挨拶の声が聞こえてきた。声の主の方を向くと銀二がいた。隣には、妻とみられる女性と、礼音くんがいる。
「こんにちは」
笑顔で頭を下げ、真央はご近所さん以上の対応をすることなく、すぐ立ち去った。気まずかったわけではない。むしろ微かに胸が波打ったことが隣の女性に対して申し訳なかった。
彼がユニクロのフリースの下から覗かせていたのは、ZAZEN BOYSのTシャツだった。今自分がカーディガンの下に着ているものと色違いだ。
メルカリにでも出そうかとクロゼットから出して放置していたが、なんとなく最後に着たくなって外に出てしまった。やっぱり売りに出さないことを決意する。
普通を自覚しながらも、それでも僅かな自意識のかけらがある自分もほほえましい。
この場所の心地よさを素直に受け入れながら、真央は箱庭の空を見上げた。
Fin
(ミドリマチ/作家・ライター)