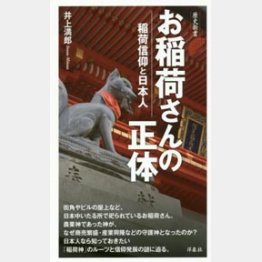「お稲荷さんの正体」井上満郎編著
江戸に多いものを称して、「伊勢屋稲荷に犬の糞」というざれごとがあった。江戸には、伊勢屋という屋号の商家、稲荷神社、そして道には犬の糞が目立ったのである。
現在、全国におよそ3万あるとされる稲荷神社の総本社は、京都の伏見稲荷大社である。有数の観光地でもあり、千本鳥居で名高い。本書は「お稲荷さん」、つまり稲荷信仰の由来を解き明かしている。
伏見稲荷大社の成立は和銅4(711)年とみられており、創建したのは渡来人の秦氏だった。秦氏は5世紀後半、朝鮮半島の新羅から先進的な文化・技術を携えて、京都に渡来した。
本来は秦氏の氏神信仰が京都で稲荷神に変容したわけだが、渡来から創建までおよそ250年を経ている。著者はこの期間を「重層」と考えている。
というのは、神社の背後に座す稲荷山は、もともと人々から神としてあがめられていた。こうした土着の山体信仰を排斥することなく、秦氏は長い時間をかけて取り込み、融和させ、「重層」して稲荷神を形成したのである。その成り立ちからして、「お稲荷さん」は原理主義的な厳格さとは無縁な、寛容で包容力のある神だったといえよう。
もともと稲荷は農業の神だった。稲穂やカギをくわえた狛狐は、豊穣な実りを象徴している。やがて狐は稲荷神の使い、さらには神そのものになっていった。やがて、稲荷は商業の神として祭られ、とくに江戸時代、大都市江戸に勧請されてからは、商人の信仰を集めて広まり、「江戸に多いもの」にまでなった。
現代の東京でも、商業ビルの屋上の片隅などに「お稲荷さん」は大切に祭られている。敬虔な信仰は、いまも生きているといえよう。(洋泉社 950円+税)