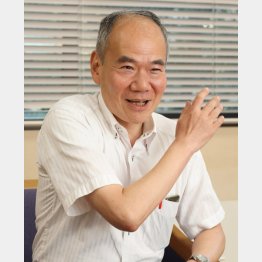「家政婦の歴史」濱口桂一郎氏
「家政婦の歴史」濱口桂一郎著
2015年、ひとりの家政婦が寝たきり老人宅に泊まり込み、7日間ぶっ通しで働いた後、死亡した。労災と認められなかったため、不当だと遺族が国を訴えたが、昨年9月、東京地裁は退け、その理由を「家政婦は家事使用人であり、労働基準法や労災保険法の適用外だから」とした。遺族の弁護人は「それは憲法違反ではないか」と主張した──と報じられた。
著者は裁判所と弁護人両者の見解を「おかしい」と感じ、「戦後日本の労働法制の根本に潜む矛盾を集約するような問題だ」と思ったという。
「その家政婦は“家政婦紹介所”に登録し、連日、家事業務と介護業務を計19時間行っていたのですが、彼女は本来『女中』を指す家事使用人ではなく、家政婦でした。労基法で家政婦と家事使用人は別立てなのに、東京地裁は彼女を家事使用人とみなしたのです。遺族の弁護人も、東京地裁が家政婦を家事使用人とみなしたことには疑問を持たなかった。両者とも、家政婦と家事使用人の違いを認識できていません」
家事使用人は労基法成立の1947年から労基法の保護から排除されているが、施行規則に労基法の適用事業として弁護士、司法書士、速記士会などとともに「派出婦会」なるものが含まれている。別名、家政婦会。つまり「家事使用人は労基法の適用除外だが、派出婦(家政婦)は労基法の適用対象」と明示されているのに、裁判所や弁護士すら気づいていなかったのだ。こうした歴代の法規に照らして家政婦の歴史を掘り下げたのが本書である。まず驚かされるのが家政婦の始まりについてだ。
「1918(大正7)年、東京市四谷区(現新宿区)で、大和俊子さんという銀行員の妻が『中産階級の主婦が暇な時間に他の家庭の裁縫や洗濯などを手伝うといい』と発想し、ニュービジネスの『派出婦会』を立ち上げたんですね。家父長制の家に住み込み、無限定に働く女中とは全く違い、自宅や宿舎から通って契約した時間に働く近代的女性労働者として誕生したのです。その年、リベラルな文化人・羽仁もと子主宰の『婦人之友』に絶賛する記事が載っています」
当初、自己実現的に働くハイソな主婦が「派出婦」だったわけである。派出婦のなり手も彼女らを求める家庭も、瞬く間に増えていく。やがて婦人雑誌が派出婦を「主婦代わり」の意味で使った家政婦という呼称が一般化するのに並行し、雨後の筍のごとく同業者が全国に現れ、皆が派出婦会と名乗るように。おのずと派出婦たちが、当初のような「ハイソ主婦」でなくなっていく。
「家政婦過労死事件」でねじれた理解が露呈
家政婦と法律に齟齬が生じるのは戦後。労基法の翌1948年、職業安定法がネックとなった。
「職業安定法はGHQ主導の法律で、労働組合以外の労働者供給事業が全て禁止になるんです。そこで、派出婦会は“求職者を求人者に紹介し、就職すれば手数料を受け取る仕組み”という仮面をかぶって生き残りを図った。そのため、書類上、家政婦が個人家庭に直接雇用されるという位置付けに変わったため、家事使用人と混同されるようになってしまったんでしょう」
結果、冒頭の「家政婦過労死事件」に、ねじれた理解が露呈したのだ。「労基法施行75年後に、労基法を作った人たちにとって想定外の事態が発生したとは皮肉だ」と著者。
ほかにも、戦前の女中の境遇が描かれた小説の抜粋や、国勢調査での家政婦、家事使用人の扱われ方と人数の変遷など、読みどころ満載の一冊だ。
(文藝春秋 1100円)
▽濱口桂一郎(はまぐち・けいいちろう) 労働政策研究・研修機構労働政策研究所長。1958年生まれ。東大法学部卒業後、労働省、欧州連合日本政府代表部一等書記官、東大客員教授、政策研究大学院大学教授などを歴任。日本型雇用システムの問題点を中心に広く労働問題を論じ、「働く女子の運命」「ジョブ型雇用社会とは何か」など著書多数。