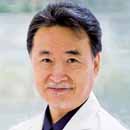よくある介護の悩み(7)徘徊を繰り返す場合はどう対処すればいい?
認知症の患者さんを自宅で介護されている方からよく聞かれる悩みに「徘徊」があります。認知症の周辺症状のひとつで、見当識障害や記憶障害などが原因で起こります。時刻、日付、場所、人物がわからなくなって、昼夜を問わずうろうろ歩き回り、そのまま行方不明になったり、事故やケガの原因になるケースもあります。しかし、本人は徘徊や問題行動の意識はなく、一生懸命に生きているのです。
認知症の方が徘徊を繰り返すと、介護者は心配や不安で心身が休まらず大きな負担になります。徘徊が深夜に起こって捜しに出たり、警察や他人を巻き込むトラブルに発展する場合もあるため、介護者にとっては大きな悩みの種といえます。
ただ、当院に寄せられる相談には、徘徊に関する悩みはそれほどありません。徘徊の症状がある場合は、おそらく精神科などに直接行かれるのだろうと思います。当院に入所された場合は、「日中は寝て、夜に起きて活動する」という昼夜逆転の生活リズムを正常に戻します。以前もお話ししたように、昼間は寝かさないようにしっかり起こし、日中に1周220メートルの廊下をどんどん徘徊していただき、体を動かし続けることで、夜間は睡眠薬治療も行い昼夜逆転の生活リズムを改善するのです。ですから、入所期間中はもちろん、自宅に戻られてからも深夜の徘徊はなくなります。