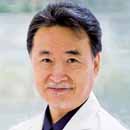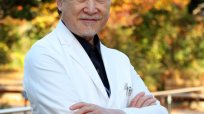よくある介護の悩み(1)夜眠れずに昼夜逆転…どうすればいい?

今回から、認知症の方を介護されているご家族からよく相談されるケースについてお答えしていきます。まず、多く寄せられるのは「昼間は横になっていて、夜は眠らずに動き出すので困っている」という悩みです。通常、昼間は起きて夜に寝る、という生活パターンが当たり前の健康的なリズムです。しかし…
![]() この記事は有料会員限定です。
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り1,431文字/全文1,572文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】