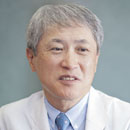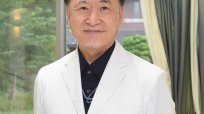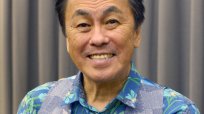体内に設置する「医療材料」は人工物だと限界がある
一方、生体弁は自身の弁に近く血栓ができにくいという利点があります。しかし、耐久性が低いので劣化が避けられません。若い人ほど劣化が早く、成長期の子供も含め35歳未満では早い人だと10年以内、35歳以上では15~20年くらいで硬くなったり、穴が開いたりしてきます。そうなると、弁を交換する再手術が必要になります。
このように、前回触れた血管修復パッチを含め、人工弁や人工血管といった人工物を手術で体内に設置した場合、一時的に問題なく受け入れられても、その後もずっとそのままの状態を維持できるケースはほぼありません。生体がどこかのタイミングで人工物を“異物”とみなし、拒否して排除しようとします。そこでさまざまなトラブルが発生し、再手術が必要になるのです。その最たるケースは細菌感染で、動脈硬化の進展による石灰化や人工物の経年劣化なども原因になります。
■かつて凍結大動脈弁を使ったことも
こうしたトラブルをなるべく減らすために、私はかつて凍結保存された大動脈弁=ホモグラフトを使った弁置換術を実施していたことがあります。ホモグラフトは亡くなった方から提供された弁を冷凍保存して、必要とする患者さんが現れたときに移植に使われます。ほかの人工弁に比べて血栓ができにくく、細菌感染に強いというメリットがあるとされています。術後に抗凝固剤の長期服用はもちろん、免疫抑制剤を飲み続ける必要もありません。