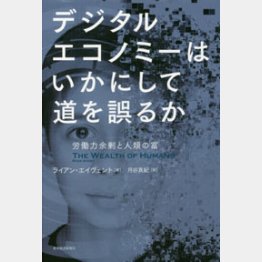デジタル革命で得た富は誰のものなのか
「デジタルエコノミーはいかにして道を誤るか」ライアン・エイヴェント著、月谷真紀訳/東洋経済新報社 1800円+税
人工知能の発達で仕事がなくなるぞと悲観視するだけでも、仕事しなくても生きていけるぞと楽観視するだけでもない。近未来論というよりも、これまでの30年のデジタル革命で何が起きたかを踏まえつつ、また19世紀の産業革命の経験から学ぼうとする、地に足のついた議論だ。
それは、政治経済学の古典、アダム・スミスの「諸国民の富」を意識した「人類の富(THE WEALTH OF HUMANS)」という原題に示されている。いわば「デジタル革命の政治経済論」。
自動運転やほとんど人のいない製造工場が可能になることで、人の手には自動化できないような高度な仕事か、または自動化するコストより安くあがる仕事しか残らないとよく言われる。だから子どもには教育投資を、というのが一般的な話の流れだが、著者はそもそもこの富は誰に帰属すべきものなのか、という問いを立てる。
だって、「もし10代のビル・ゲイツが10代のソマリア人の若者と入れ替わってソマリアで暮らし、ソマリア人の若者がアメリカで暮らしていたら、ゲイツはそのソマリア人より貧しい人生を送っただろうことはほぼ間違いない」のだから。
個人の努力は大事だが、個人の能力を開花させられる土壌を無視するのはフェアではない。この土壌を著者は「ソーシャル・キャピタル(社会資本)」と呼ぶ。アップルのような企業文化の中でiPhoneは開発されるが、その企業文化はシリコンバレーで培われ、それはアメリカ合衆国という国家の中にある。では、スティーブ・ジョブズが度外れた大金持ちになって、あとの人々の賃金がまったく上がらないような事態は、本当に「仕方のない、そういうもの」なのか。
雑誌「エコノミスト」の国際経済欄を長く担当してきたという著者は、これを道徳ではなく経済の言葉で、経済の問題として語る。なぜならそのソーシャル・キャピタルが知らず知らず侵食されていけば、結局は私たちが経済成長の基盤を失うことになるから。私たちは、デジタル革命のもたらす未来(「破壊的変革」)に目を奪われざるを得ない。しかし同時に、それがどのような政治経済的文脈の中で展開しているのか、人工知能をひとつの「技術」とみた上で、それが生み出す富は誰に帰属すべきなのか、またそれは誰のためなのか、過去から学ぶ姿勢も忘れないでいたい。
政府が必死に賃上げを要請するこの日本も、もちろん例外ではない。