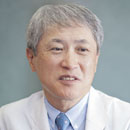患者にしっかり向き合って力を尽くす医師が減ってきている
前回、最近の若手医師の傾向として、「担当した患者さんに対し、きちんとフォローせずに放置するタイプが増えている」とお話ししました。「病気を治したい」と望んでいる患者さんにきちんと向き合い、病気に対する不安を取り除くために寄り添って力を尽くすことは、医師にとって当たり前の姿勢です。しかし、近年はそうした意識を持った医師が減ってきているといえます。
それに該当するケースとして、冒頭のタイプのほかに、自分が理想としている治療や自己管理を患者さんに押し付ける医師も増えています。たとえば、心臓にトラブルがある患者さんでは、心臓病の代表的なリスク因子である高血圧、高血糖、高コレステロール、肥満をきちんとコントロールできていないケースが多くあります。そのため、患者さんには、食事の制限や運動習慣を身に付けるなどの自己管理を徹底してもらうことが理想的です。
しかし、いくら間食は避けて全体的な食事量を減らし、毎日ウオーキングをして、十分な睡眠をとりましょうなどと言っても、きっちり自己管理を継続できる患者さんはほぼいないといえます。患者さんにしてみれば、いまの仕事をしながら、毎日の食事と運動に気を配り、ぐっすり眠る生活はとてもできない……そう考える人がほとんどでしょう。そうした自己管理ができないことで心臓にトラブルが出たから、なにか別の解決策はありませんか? といった思いもあって病院に来ているのに、「自己管理ができない患者は治せない」と、医師が最初から蓋をして突き放してしまったら、患者さんはどうすることもできなくなってしまいます。