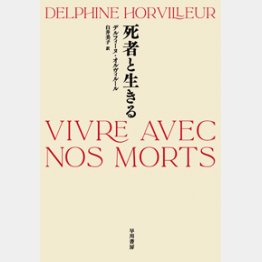「死者と生きる」デルフィーヌ・オルヴィルール著 臼井美子訳
コロナ禍においては、葬儀の形式も変化した。2020年には家族葬が40.9%、一般葬は48.9%だったのが、22年には家族葬が55.7%、一般葬が25.9%と一般葬が半減した。
フランスでわずか3人しかいない女性のラビ(ユダヤ教の宗教的指導者、聖職者)である著者は、コロナ禍の葬儀のエピソードを伝える。
ある一家から、父親の死に際して、感染を恐れて葬儀には誰も呼べないので、著者に電話で祈りの言葉を捧げてほしいと頼まれた。電話で祈りを終えた著者は呟く。
「死と自宅とが交わらないように隔てるものなんて何もない。死はわたしたちの人生の舞台に許可なく入り込んでいた」
著者は1974年、フランス東部の都市ナンシーのユダヤ人家庭に生まれる。17歳でイスラエルへ行き医学を学ぶが、その後ジャーナリストに志望を変更、フランスのテレビ局に勤めるが、ラビになるために退職して、ニューヨークでラビ養成講座を受講。現在はフランスのリベラルなユダヤ教宗教団体MJLFのラビとして活動している。
本書は、この型破りの経歴を持つ著者が執り行った葬儀や親しい友人たちの死を通して生と死の意味をつづったもの。
「シャルリー・エブド襲撃事件」の犠牲者の一人、精神科医のエルザ、アウシュビッツからの生還者でフランス人に最も敬愛される女性といわれる政治家のシモーヌ・ベイユ、重い病にかかり、子どもの成長する姿を見ることなく逝ってしまった友人のアリアーヌ、墓にスプレーでかぎ十字がかかれ、墓石がひっくり返されたアルザスのユダヤ人墓地に眠る「エドガーおじさん」……。
それらの人たちの思い出の合間に聖書やタルムード(ユダヤ教の口伝律法)の逸話が織り交ぜられ、ユダヤ教の死に対する独特の考えが紹介される。
静謐(せいひつ)な文章の中から、生と死という普遍的な問題に真摯に向き合う著者の誠実な心が伝わってくる。 <狸>
(早川書房 2750円)