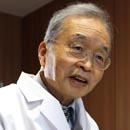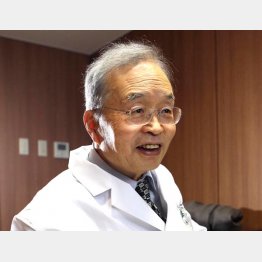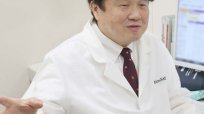かつては日本版の「看取りのパス」が使われていた
該当する緩和病棟を直接見たわけではないので、勝手なことは言えません。ただ、患者は死を受容していたとしても、きっと心の奥には「生きたい」という気持ちが残っていると思うのです。臨終期にあって、医療者には、生きていていいんだよという心、命を惜しむ心、別れの悲しみ、哀れを感じる心、未練を肯定する心があると思うのです。ですから、スタッフにはむしろ迷いやためらいを捨てて欲しくないと私は思います。
アメリカの精神科医で医療人類学者のアーサー・クライマンは、著書「病いの語り」の中でこう記しています。
「死を迎えるにあたって……ひとつの不変の道などないのである。……どのような方法が最良の選択なのかを、あらかじめ知ることはできない」
また、聖路加国際病院名誉院長で105歳で亡くなられた日野原重明先生は、「日本の生死観大全書」の中で「ホスピスでは……患者ひとりひとりに個別的にタッチするということが必要で、全体をまとめてマスとして扱うことはできません」と述べています。
実はイギリスでは、看取りのパスがまだ回復の余地がある患者にまで適応されたとの告発が続き、2014年に国として全面禁止したといいます。その後、日本でも看取りのパスの報告は見つからなくなりました。