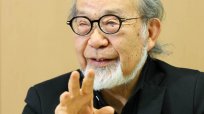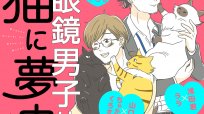職場にいるのは身分確保のため? 必要とされていない現実を直視したくない人たち
有益と思えないことに忙殺される人
建物の外に出ると、大学前の広場で学生たちがパーティーに向けた予行演習をしていた。スウェーデンの昔ながらの新学期パーティーで、体操選手のチームのような動きを見せる学生もいれば、もっと派手な動きを見せる面々もいる。みんな楽しそうだ。
ボルボに乗ってデンマークへ戻る道すがら、ポールセンから聞いた職場で何もしない人たちのことを話し合った。それは本当だろうか? コペンハーゲンへ入る橋にさしかかるころには、中身のない仕事か、中身の充実した仕事か、という概念上の二者択一では状況をとらえきれないことに気づいた。
たいして重要ではないが、自分では仕事だと思っていることをしていたり、少なくとも賃金をもらって仕事に似た何かをしたりしている人はたくさんいる。必ずしも有益だとは思わないまま、この種の仕事に忙殺されている人さえいる。
「中身のない仕事」に代わる概念が必要だった。難しくないのにストレスフルな仕事や、人にうまく説明できない仕事、人から説明されてもよくわからない仕事もカバーする概念だ。「偽仕事(pseudowork)」という言葉が適切だと私たちは考えた。
偽仕事という概念は、命じられてする仕事から賃金をもらってする仕事、組織に求められてする仕事、仕事のようで仕事でない仕事まで、より広い範囲をカバーできる。何もしていないと思いながら時間を費やすのも偽仕事であり、仕事のなかで意味がないと感じる部分も偽仕事である。
「偽(pseudo-)」という接頭辞はギリシア語のプセウドス(pseudos)に由来し、噓や偽りを意味する。単語のはじめにこれをつけると、そのあとに続くものは見かけと異なるということになる。たとえば偽名(pseudonym)は本当の名前ではない。偽科学(pseudoscience)は本物の科学ではない。
その仕事は必要かつ重要で、ぜひともなくてはならないと思われていて、多くの人から仕事と認められていて、給料が払われているかもしれない──称賛や賞すら受けているかもしれない。だがスウェーデンから帰国する橋の上で、私たちは気づきはじめた。本物の仕事は、われわれが仕事と思って賃金を払っている仕事よりもはるかに少ないのではないか。もっと休みを取れるのでは? もっと望ましいことにエネルギーを使えるのでは?
週15時間労働が実現しなかった理由は、偽仕事にあるのではないだろうか?
【著者】
▽デニス・ノルマーク
1978年生まれ。デンマークの人類学者、講演家、著述家。オーフス大学で人類学の修士号を取得したのち、長年にわたってコンサルタントや企業の社外取締役として働き、現在はフリーの講演家およびコメンテーターとして国際的に活動している。英訳された『Cultural Intelligence for Stone-Age Brains』など、文化や文化の差異についての著書がある。
▽アナス・フォウ・イェンスン
1973年生まれ。フリーで活動するデンマークの哲学者、著述家、劇作家、講師。パリのソルボンヌ大学で哲学の修士号、コペンハーゲン大学で博士号を取得。英訳された『The Project Society』や『Brave New Normal: Learning from Epidemics』など10冊の著書があり、そのほとんどが現代社会と私たちの現状を論じたものである。ウェブサイトはwww.philosophers.net およびwww.filosoffen.dk。
【訳者】
▽山田文
翻訳者。訳書に『ステイ・スモール 会社は「小さい」ほどうまくいく』(ポール・ジャルヴィス、ポプラ社)、『地球の未来のため僕が決断したこと 気候大災害は防げる』(ビル・ゲイツ、早川書房)、『「歴史の終わり」の後で』(フランシス・フクヤマ、マチルデ・ファスティング、中央公論新社)などがある。