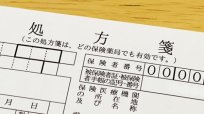薬物乱用防止教室で話していること…物質ではなく「人」に依存する
多くの学校薬剤師は、担当校において「薬物乱用防止教室」を実施しています。私も小学生や中学生を対象に、毎年薬物乱用防止教室を行っています。薬物といっても、大麻や覚醒剤といった禁止薬物の話は少なめで、これらの入り口(ゲートウエードラッグ)となりやすい「たばこ」や「アルコール」の話題が中心です。
これに加えて、最近は市販薬によるオーバードーズ(OD)について取り上げています。古くは「シンナー」、そして「脱法ハーブ」や「危険ドラッグ」、最近は「市販薬によるOD」と、時代とともに乱用薬物は変わってきていますが、ある物質が規制されたとしても、次から次に新たな依存物質が出てきます。
広く「依存症」として考えると、アルコールや薬物のように化学物質への依存(物質依存)以外にも、ギャンブル、ゲーム、買い物など行動への依存(行動嗜癖)もよく知られています。アルコールや薬物を摂取したり、ギャンブルやゲームをすると脳の報酬系という回路が刺激され、これらの行為を本人の意思とは関係なく反復するクセがついていきます。そしていったんクセづいてしまうと、これらの行為を止めようとした時にイライラしたり、気分が落ち込んだり……といった不快な離脱症状が起こります。
依存症は誰にでも起こる現象で、深みにはまる前に信頼できる家族や友人など誰かに相談することがとても重要です。行為や物質に依存するのではなく、「人」に依存する、人とつながる。言い換えると、安心して相談できる人を持つということが、何よりも大切ではないかと思うのです。