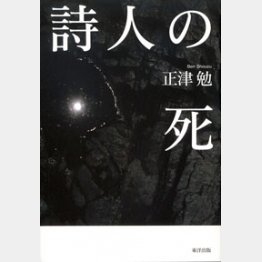「詩人の死」正津勉著
北村透谷から寺山修司まで、今なお読み継がれる珠玉の詩を残して足早にこの世を去った詩人たちの作品と、その死までの足跡をたどった一冊。
北村透谷の死の予兆を彼の詩の変化に見いだし、石川啄木の詩に織り込まれた舶来化した言葉の中に絶望しきった悲しさを読み取る。「どうも間もなく死にそうです」とつづった宮沢賢治、「死と私は遊ぶ様になった」と書いた村山槐多、「人はお墓へ入ります」と歌った金子みすゞなど、死という観点から見た詩人の内面についての考察は興味深い。
著者の姉との交友をきっかけに自身も面識があったという寺山修司とのエピソードは、死をも作品化してしまう詩人の業がうかがい知れる。
巻末にはあとがき代わりとして、谷川雁を取り上げている。95年まで生きた谷川は早世とはいえないものの、肉体の死の半世紀前に「私の中にあった『瞬間の王』は死んだ」として詩人としての自分を葬っているという指摘には、はっとさせられる。(東洋出版 1600円+税)