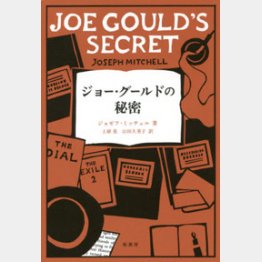「ジョー・グールドの秘密」ジョゼフ・ミッチェル著 土屋晃、山田久美子訳
読み終えて、しばらく放心した本は久しぶりである。
ジョゼフ・ミッチェルというのはアメリカの著述家。元新聞記者で、1938年から雑誌「ニューヨーカー」のスタッフライターとなった。
80年ほど前に活躍したライターであるが、近年になり日本で作品集が出版されている。この本が4冊目、最後の作品集である。
彼が書いているのは、1930年代から1940年代のニューヨークにいた市井の人々である。少し変わった人たちを取り上げている。40年間、私腹を肥やすためのダンスパーティーを開催している“ダッチ提督”や、ニューヨークにいる38家族を束ねて「ジプシーの王」を自称する男など。彼らの言葉と生活と、そして当時の街の風景を生き生きと描写している。
特段、大きな事件が描かれるわけではない。少し変わった生活と人生が描かれるばかりである。しかし、読むと心に残る。
元新聞記者による徹底した取材には感心する。たとえば「ダッチ提督」という一編には、実在しただろう人物の名前が56人ほど挙げられている。昔の市井の人名までどうやって調べたのか不思議なのだが、1930年代の新聞記者はそれぐらいのことは簡単にやってのけたのだろう。
圧巻は最後にある「ジョー・グールドの秘密」だ。奇人のひとりジョー・グールドは「ニューヨークで聞いた人々の話を書き留め、それを歴史に残そうとする『口述史』を何十年も書きためている」という人物である。彼を深く取材するミッチェル。しかし「いずれまとめて本にするさ」という言葉の背後にある思いと暗い現実が剔抉される。息をのむ思いで読み終えた。
そして、その暗く重い現実は、物書きのひとりでもある著者ミッチェルも直撃し、彼はこの一編を書いたあとに文章を書かなくなった。そのあたりは、青山南によるあとがきで解説されており、胸迫る思いに駆られる。
文章を書くことについて、考えさせる一冊である。(柏書房 1800円+税)