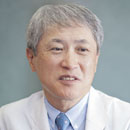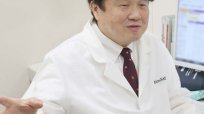大掛かりな手術では術中から血栓ができやすい状態になる
じつは、手術中の血栓形成を予防するための輸液管理については、大規模な研究結果に基づいたエビデンスがほとんどなく、ガイドラインにも記載されていません。患者さんの全身状態を悪化させないための輸液管理については目標値が定められているのですが、血栓予防に関しては医師の経験で対応しているのが現状なのです。
近年、腹部手術などでは、手術での血栓形成を予防するために手術中から「フロートロン」という医療機器を使うケースも増えています。手術を受けている患者さんの足にサポーターを巻いて、一定時間ごとに空気圧で圧迫して静脈の血行を促進するのです。ちなみに、フロートロンは患者さんの肌に接触するため感染対策の観点から“使い捨て”が一般的でした。
しかし、それではあまりにもムダが多すぎるので、3年前にわれわれと医療機器メーカーが共同で研究を進めて再利用できるタイプを開発し、国内で初めて製品化しました。もちろん、順天堂医院で実施される手術で使われています。
手術後に肺血栓塞栓症を起こして突然死を招いた“事故”として、ほかにもこんなケースがありました。ある大企業の会長が、脊柱管狭窄症の手術を受けた時のことです。その会長はもともと狭心症で冠動脈を広げるため血管内にステント(金属製の筒状の網)が入っていたため、普段から血栓を予防するために抗血小板薬を飲んでいました。しかし、その病院では手術での出血リスクを減らす目的で抗血小板薬が中止され、手術が行われました。その結果、退院の数日前に肺血栓塞栓症の診断で亡くなってしまったのです。もしかするとステント内血栓症による心臓突然死だったかもしれません。