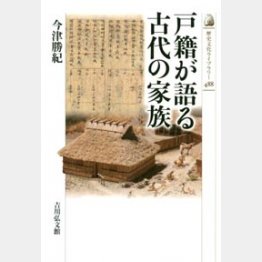「戸籍が語る古代の家族」今津勝紀著
現行の戸籍は、戦前が「家」を基本単位としていたのを「夫婦」を基本単位に変更し、併せて華族、平民といった身分事項の記載も廃止された。しかし、事実婚、夫婦別姓、同性婚といった新しい動きに戸籍の記載がどう対応していくのかは今後の問題だろう。
本書は正倉院文書などに残された古代の戸籍を手掛かりに、当時の人口動態や家族形態など古代人の暮らしぶりを明らかにしたもの。律令国家時代の戸籍は天皇に従属する人々を登録する制度であり、その目的は、課税、労働力の徴発、兵役で、いずれも成人男子に課せられる。およそ50戸を1つの単位として、そこに全戸数、戸主を筆頭にその内訳、男・女の別、それぞれの身分、身体的特徴なども記載されている。
そこから分かるのは、8世紀前半の日本の総人口は約450万人、出生時の平均余命は28・48歳、合計特殊出生率は約6・5人(2018年の日本女性は1・42人)など。また、貧富による等級は「上上」「上中」「上下」……「下下」の9つに分かれ、圧倒的多数が最下層の「下下」に属しており、現代の1%VS99%を彷彿させる。それでも、男性が60歳を越えると租税負担が半額、66歳以上なら免除、成人女性の寡婦は米などの給付対象となり、男女ともに80歳を越えると介護者が与えられるという福祉制度もあったことがわかる。
著者は戸籍やその他の文献を駆使しながら、古代の具体的な家族形態を考察しているが、特筆すべきは、古代日本の婚姻形態としてほぼ常識となっている妻問(つまどい)婚に疑義を呈していることだ。夫婦が別居し、夫が妻の元へ通うというのは、母系制社会の特徴とされてきた。しかし、ツマは男女ともに使われる言葉で、「トフ」も訪れるではなく話す意であり、妻問婚という婚姻形態の実態が現実にあったか実証できない、と。その他、戸籍という一見無味乾燥な史料から思わぬ風景が見えてくる。
日本人で唯一戸籍を持たないのは天皇家。その意味を問うた遠藤正敬の「天皇と戸籍」(筑摩書房)も併読されたい。 <狸>
(吉川弘文館1700円+税)