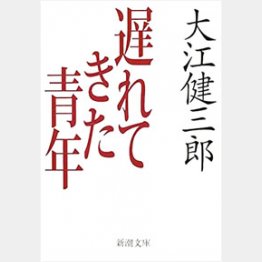左翼運動をふりかえる異色のドキュメンタリー
「きみが死んだあとで」
香港にせよミャンマーにせよ、権力に抵抗する現代の社会運動が米国のウォール街占拠などに方法論を学んだSNS時代の世界的現象なのは確かだろう。だが例外が日本。権力の不祥事が絶えないのにニッポンだけは無風。なぜだ?
そんな危機感からだろうか、かつての左翼運動をふりかえる異色のドキュメンタリーが相次ぐ。現在公開中の「狼をさがして」と来週末封切りの「きみが死んだあとで」だ。
内容の時代順でいくと「きみが死んだあとで」が新左翼運動の初期に当たる1967年10月8日の第1次羽田事件に材をとる一方、「狼をさがして」は70年代に政治運動が退潮する中、武装化して「連続企業爆破事件」を起こした「東アジア反日武装戦線〈狼〉」などの関係者のいまを追う。
67年の事件では京大1回生・山崎博昭君が機動隊とのもみ合いの中で死亡し、60年安保の樺美智子さん死亡事件とならぶ衝撃を与えた。代島治彦監督は大阪・大手前高校時代の同級生たちに取材し、18歳で散った若者の人物像を再現しようとする。題名の「きみ」は山崎君。その死からいまへどれほど時が流れたかを問うのだ。
「狼をさがして」は韓国出身のキム・ミレ監督が釜ケ崎の労働者を取材中に事件を知ったことから取材を開始したという。双方の共通点は代島監督が58年生まれ、キム監督が64年生まれと「遅れてきた」世代であること。ただし韓国では民主化運動拡大の契機となった光州事件が80年でキム監督は当時16歳だから、政治意識の違いは歴史と体験の相違でもあるだろう。
そういえば大江健三郎著「遅れてきた青年」(新潮文庫、817円)の青年主人公のいう「遅れ」は「戦争に乗り遅れ」て皇国のために殉じそこね、時流に屈服したと感じるよじれた劣等感だ。その中に戦後日本の「何か」を解くカギが潜むかもしれない。 <生井英考>