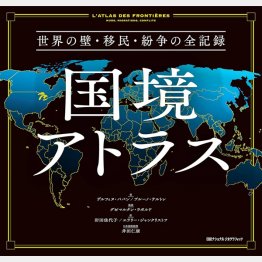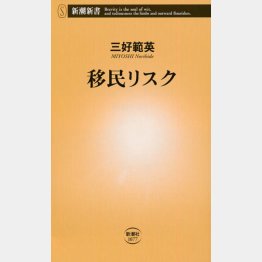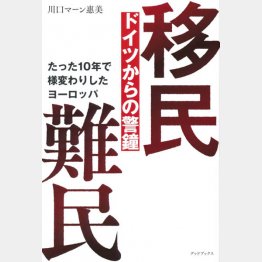移民とニッポン
「国境アトラス」デルフィヌ・パパン、ブルーノ・テルトレ著、岩田佳代子ほか訳
日本の総人口が14年連続で減少と総務省が発表。では移民に頼るか、と簡単にはいかなそうだ。
◇ ◇ ◇
「国境アトラス」デルフィヌ・パパン、ブルーノ・テルトレ著、岩田佳代子ほか訳
1期目は米国とメキシコの間に壁を建設するとほえたトランプ政権。今期は強引な強制送還に打って出た。しかし実は国境問題はアメリカだけの難問ではない。
各地で紛争や戦争のたびに難民があふれ、その受け入れに肯定的だった西欧諸国はことごとく反発する右派勢力が選挙で躍進した。中国の海軍力増強に見られる東アジア有事への懸念も海上の国境争いなのだ。
本書はこうした状況をふまえ、フランスの地政学の専門家たちが編んだ世界中の国境をめぐる図解集だ。
歴史的にみると国境は近代になるまで曖昧なものだった。山脈や河川などが区切りとなった自然な国境は、いま世界では55%。対して地図上に直線で記されるような人為的な国境は45%という。
どきっとするのは「壁と移民」の章。スペインとモロッコ、ハンガリーとセルビア、アメリカとメキシコ、韓国と北朝鮮など政治・社会対立が築く壁がいかに厳しいフィルターになっているかが一目でわかる。風光明媚な地中海も本書で見ると、アフリカから北上を試みる難民たちが命を危険にさらす海の墓場の様相を呈しているのだ。四方を海で囲まれて国境問題にうとい日本人の学ぶべき世界地図だ。
(日経ナショナルジオグラフィック3630円)
「移民リスク」三好範英著
「移民リスク」三好範英著
日本で移民問題というと、クルド人問題や非人道的な入管行政などがすぐに挙がってくる。少子高齢化と急速な人口減少に対しては移民政策を変えることが必須という声も少なくない。これに警鐘を鳴らす著者は読売新聞の元特派員。
たとえば「ワラビスタン」の異名をとる埼玉県の川口市・蕨市を現地取材し、2023年夏に川口で起こったトルコ人とクルド人の抗争から病院前で大混乱が起こった事件が社会問題化への大きな節目になったという。難民として入ってきた若者たちが常に刃物を隠し持っていることがわかり、日本人社会が強い違和感を示すようになったのだ。
他方、著者は幼いころに親に連れられてきたクルド人の若者たちにも取材。彼らの意見を聞き出すとともにトルコのクルド人地区にも取材に出かけて現地の声を聞き取っている。一口にクルド人といっても思想や志向は多様で、自己主張や自己弁護に終始するとは限らない。多文化共生に意欲的な川口市政も直接取材したうえで、関係諸機関の連携がないなどの欠点も指摘。単純な排斥論でも受け入れ論でもない見方を探る姿勢には好感が持てる。
(新潮社 968円)
「移民難民」川口 マーン 惠美著
「移民難民」川口 マーン 惠美著
ドイツにピアノ留学して以来、すでに40年以上のドイツ暮らしを経験してきた著者。生活者すなわち一般のドイツ市民の立場からの日独比較でエッセイストとしても知られるが、近年はドイツ批判の急先鋒。特に2015年、当時のメルケル独首相が中東難民に門戸を開いたことを著者は厳しく批判する。
またメディアもメルケルの肩を持つばかりで、移民の若者による暴力事件や犯罪の真相を伝えることもしないという。ナチス時代の反省からドイツは戦後一貫して人道国家の制度と評判を築き上げてきたが、そのタテマエが自縄自縛となってドイツの混乱を招いているわけだ。周辺の欧州各国も同じ難民でもウクライナ難民は歓迎だが、シリアなど中東の難民はお断りとするなど自分勝手な実態が露見している、と。
本書は直近10年ほど日本の雑誌やウェブマガジンの記事を集めたものだが、どこを切ってもドイツ批判が噴き出す。終章は日本への警告。「外国人が多くなりすぎると、治安は不安定になり、文化や伝統が崩れ、国家は最終的に原型をとどめなくなる。それは、すでにそうなりかけているドイツやフランスが、十分に証明してくれている。その二の舞いになることだけは、絶対に避けるべきだ」
(グッドブックス 1650円)