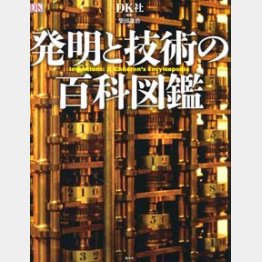「発明と技術の百科図鑑」DK社編著 柴田譲治訳
心電図検査でお世話になる「心電計」。心臓で生じる電流を測定するこの装置を1901年に発明したのは、オランダ人医師のウィレム・アイントホーフェンという人物。
今や家庭用まで出回っている心電計だが、当時の心電計は、電極代わりに塩水入りのバケツに手足を入れなければならず、装置もちょっとした家具ほどの大きさがあった。
また誰もが毎日のようにお世話になる電子レンジは、1945年にアメリカ人技術者のパーシー・スペンサーが発明したのだが、実はその発明は偶然の産物だった。
電磁波の一種であるマイクロ波を発生させる「マグネトロン」の実験をしていた際、氏がポケットに入れていたチョコレートが溶けていた。それで、マイクロ波が板チョコの水分を振動させて熱を発生しチョコレートを「調理」していたことに気づき、電子レンジが生まれたという。
本書は、人類の生活を一変させたこうした偉大な発明や技術を紹介する豪華カラー図鑑。
人類最古の発明である石器から、車輪や火薬、電気、自動車、宇宙開発など、発明と技術の発展の歴史を一望する。
コンピューターやインターネット、スマホなど、今まさに私たちが体験している技術や発明の項も興味深いのだが、1864年に発明され、当初は足踏み式だったという歯科治療用の機械式ドリルや、水洗トイレは1596年にイングランドの詩人が発明したもののパイプから悪臭が戻ってくるため普及せず、その後200年近く経った1775年に、スコットランドの発明家がS字型水封トラップ(Sベント)を使うことで悪臭対策に成功してから評判となったなど、空気のごとく、あって当たり前のように使っている身の回りの日常の品々のエピソードが面白い。
(原書房 5000円+税)