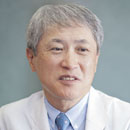患者にしっかり向き合って力を尽くす医師が減ってきている
さらにいえば、そうした患者さんたちがいるから、医療が進歩してきたともいえます。たとえば「無輸血手術」が、そのひとつです。
宗教上の理由から、輸血を受け入れない患者さんがいます。「他から血液はもらわない、自分の体からいったん出た血液も戻さない」といった信仰上の強い意志を持っています。そのため、かつては「輸血への同意がなければ、大出血の可能性がある手術は行えない」として、受け入れを拒否する病院があり、いまでもみられます。
しかし、そんな患者さんに対して私はこれまで拒否するような対応はせず、「無輸血」でこれまで20人以上の心臓手術を行ってきました。どんな場合でも患者さんに寄り添うのが医師の使命だと考えているからです。まずは患者さんの希望を聞き、可能な限りその意向に沿った治療を行うのが医師の仕事なのです。
「輸血をしない」というのが患者さんの希望ならば、「できるだけ出血の少ない手術をする」ことを目指すのです。基本は患者さんの体内にある血液しか使わない。当時は高いハードルの挑戦でしたが、その実現のために、なるべく出血が少なくなるような手順や迅速な止血の方法を考えたり、メスを入れると同時に止血できる医療器具を活用したり、術前術後で使う薬を工夫するなどして、無輸血手術を成功させました。