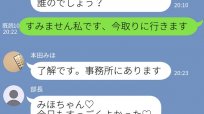探検家・関野吉晴さん 映画「うんこと死体の復権」を監督「“鼻つまみもの”を観察する3人に魅了された」
関野吉晴(探検家)
うんこは流し、死体は焼くものである──。そんな“常識”を打ち破るのが、映画「うんこと死体の復権」(3日からポレポレ東中野ほか全国順次公開中)だ。字面でギョッとするなかれ、普段は忌み嫌われる「鼻つまみもの」をテーマに据えた硬派なドキュメンタリーである。うんこや死体を通じて描かれる自然の循環の輪とは何か。本作で初めてメガホンを握った希代の探検家に「鼻つまみもの」の魅力を聞いた。
◇ ◇ ◇
■「お返しの野糞」の土は爽やかな味
──本作は「うんこ出ましたー!」のひと言から始まります。監督自身が林の中でしゃがみ込んで野糞をしたり、その1カ月後に野糞した場所の土を食べたり、衝撃的なシーンが満載です。
野糞してから1週間以内は絶対に食べませんが、だいたい1カ月経つと安心して食べられます。口にしたのは団粒土と言って、ミミズが食べてお腹を通った土。農地に最適な土ですね。映画の中でも言いましたが、食べてみると爽やかな味がしました。
──そもそも、なぜ野糞を?
この作品の主役は、約50年間にわたり野糞をし続けている「糞土師」の伊沢正名さん、玉川上水の生き物のリンクを調査している保全生態学者の高槻成紀さん、死体に群がる虫を描く絵本作家の舘野鴻さんの3人。伊沢さんはもともとキノコやコケ、変形菌などを撮る写真家で、菌類を観察しているうちに「俺は彼らに何をお返ししているか?何もない」ということに気が付いたといいます。その「お返し」が野糞だった。野糞を始めた当初は「病気を蔓延させるんじゃないか」などと非難されていた。「土になるから」と訴えても、証拠を求められる。それで野糞をした場所の掘り返し調査を始めた。約1カ月で土になり、口にしても安心。いい土になるのだということを伊沢さんは確かめたかったわけです。
──なぜ、あえて「うんこと死体」をテーマに据えたのでしょうか。
50年前から探検家として南米アマゾンに通ったり、さまざまな伝統社会を目の当たりにしたりしてきました。そうした暮らしの中でもっとも関心を寄せたのが、都会の住民と彼らの違い、すなわち人間と自然との関係でした。アマゾンの人々は、自然の中で完全な循環の輪の中に入っている。うんこも死体もゴミも全部森に捨て、それが土になり、植物の栄養になり、動物が食べる。そして人が動植物を食べ、またうんこをしたり、ゴミを捨てたり。一方、都会に住んでいる限り、こうした循環の中には入れない。うんこも死体もゴミもすべて焼いてしまって二酸化炭素を出すだけで、まったく役に立たない。そうして「人と自然の関係がどうあるべきか」を考える中で、うんこと死体を執拗に観察し続ける主人公3人の発想に惹かれたから撮る気になったのです。