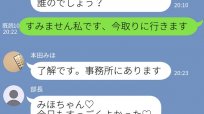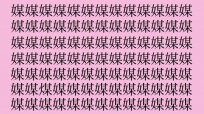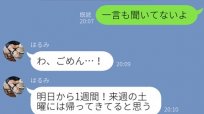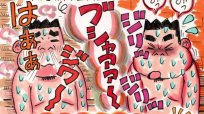なぜスマホ、AIの進展で労働時間は減らないのか…望ましい労働は「一日4時間」?
必要ないのに働くなんてどうかしている
パソコン、インターネット、スマートフォン、生成AIーー。
さまざまなテクノロジーが発展して人間の業務はどんどん効率化が進んでいる。にもかかわらず、人々の労働時間が劇的に短くなったという話は聞かない。むしろ、はるか昔よりも私たちは長く働いている。
なぜ労働時間が短くならないのか。働かずにはいられない人の心理、そしてそれにつけ込む「偽仕事」がどこにでも介在していることが背景にある。100年余り前の第一次世界大戦(1914〜1918年)時に経済が繁栄した現象をひもといて考えてみると、それが見えてくる。
「偽仕事」を追い出して生産性と充実度が本当に高い働き方を現実世界でやり切る術を提案したデンマークのベストセラーの邦訳版『忙しいのに退化する人たち やってはいけない働き方』(サンマーク出版)より一部抜粋、再構成してお届けする。
◇ ◇ ◇
1932年、当時60歳だったイギリスの哲学者バートランド・ラッセルが「怠惰への讃歌」と題したエッセイを発表した。パラメーターを1ついじるだけで、まったく新しい社会を築こうという提案だ。「労働時間」というパラメーターである。
着想のきっかけは第一次世界大戦。ラッセルが驚いたのは戦争そのものではなく、戦争中に経済が繁栄したことだ。かなりの労働力人口が、弾丸をつくったり、「花火を知ったばかりの子ども」のように夢中でそれを発射し合ったりするのに大忙しだったにもかかわらずである。
半数を超える労働力人口が戦争に従事していたのに経済が繁栄したのだから、平時にははるかに短い労働時間でやっていけると思われた。1932年、ラッセルは「一日4時間労働」を提案する。当時の知識人の多くがそれに賛成した。
では、第一次世界大戦後に一日4時間労働が導入されなかったのはなぜだろう? ラッセルの考えでは「奴隷国家の道徳」のせいであり、宗教のせいだ。プロテスタントは労働そのものを尊び、神に選ばれた者の証と見なす。労働時間が減ると、大人は飲酒に、子どもはいたずらに走るという主張も多かった。
ラッセルは、それと正反対のことを示したいと望んでいた。暇は個人だけでなく文明全体にとって望ましいと示したかったのである。
ラッセルのエッセイが興味深いのは、人々が家に帰って休まずに働き続けることに疑問を呈している点だけではない。労働者が4時間だけ働いて家に帰る社会は、よりよい暮らしだけでなく、より気高い文化にもつながるとラッセルは考えていた。文明の大進歩、偉大な芸術作品、重大な科学の発見は、労働者が生み出すわけではない。暇という贅沢を享受する階級から生まれるのである。