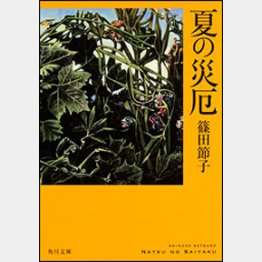「夏の災厄」篠田節子著
日本脳炎はウイルス感染症のひとつで、日本では1966年の2017人をピークに減少し、92年以降は毎年10人以下を推移している。本書は、その日本脳炎が変異しパンデミックを起こすという、現行のCOVID―19を彷彿させる予見的な小説である(親本は1995年刊)。
【あらすじ】堂元房代は元看護師で、退職後は孫の子守に明け暮れていたが、亭主が定年退職したのを機に、地元埼玉の昭川市保健センターに復職した。
ある晩、センターに頭痛を訴える男がやって来た。医師の診断は熱中症だったが、光をまぶしがり誰も香水などつけていないのに甘い香りがするという。そういえば昨日も同じことを言っていた患者がいたが、2人の患者が相次いで急変し、死亡。市内の富士大学付属病院は日本脳炎と診断。しかし日本脳炎は蚊の媒介によるもので、蚊のいない4月のこの時期に発症するのはおかしい。その後も昭川市の特定地域から感染患者が大量に発生、しかも異例の高い死亡率を示している。一体何が起きているのか。房代は保健センターの職員、小西と町医者の鵜川と一緒に情報を集めていく。
そこでわかったのは、4年前に同じような症状の病気がインドネシアのある島で大量発生していたこと、その発生には富士大学病院が関わりがあるらしいこと等々。そうしているうちにも感染は拡大し続け、ついには県外にも広がっていく……。
【読みどころ】特筆すべきは、昭川市内の飲食店をはじめとする店舗の従業員に自宅待機を命じたり、感染地域の児童がいじめにあったり、ワクチン接種における行政の混迷ぶりがリアルに描かれていること。物語はひとつの町の出来事だが、著者も同様のことが四半世紀後に全国規模で本当に起きるとは予想していなかっただろう。 <石>
(KADOKAWA 924円)