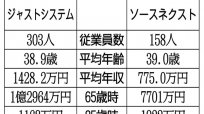公表された重点施策で露呈…JR東海の株価低迷と時代遅れの収益構造
JR九州と比べれば違いは顕著だ。これといったドル箱路線がないJR九州の営業収益では運輸は4割足らず。その代わり不動産・ホテルの収益がこれに次ぐ3割超を占める。将来的な人口減少で、鉄道事業が先細りするのは確実。JRに限らず、どの私鉄も「鉄道外」収入の確保に躍起だ。ところが今回公表されたJR東海の重点施策では、「輸送」「リニア」が中心。果たしてこれを投資家はどう見るか。
もっとも当事者のJR東海だって、こんなことは先刻承知だろう。とりわけ22年3月期には2年連続の最終赤字を計上したコロナ禍が同社に与えたショックは大きかった。同年末には「グループビジョン2032」を打ち出し、そこには「従来のビジネスモデルから脱却しなければ、将来にわたって成長することはできません」とつづられていた。
「22年という年は1987年に国鉄が分割・民営化して、JR東海が発足して以来、最大の画期の年でした。コロナ禍による大打撃もさることながら、この年の5月に同社に君臨してきた葛西敬之名誉会長が亡くなったからです。葛西氏は晩年は安倍晋三元首相の最大の後見人として国士然とした発言で知られましたが、『国商』と形容されたように、鉄道事業こそが国を支えるという信念でJR東海を支配してきた。そして『国家事業』としてのリニアを置き土産にして世を去った。葛西さんが亡くなったからこそ同社は事業の多角化も打ち出せたんです」(同前)
2月の第3四半期決算では、年間の売り上げを上方修正、コロナ禍前の20年度1兆8000億円台に迫る1兆7880億円を見込む。しかし葛西氏の“置き土産”の重しのせいか、株価はなかなか上向いてはくれない。
(ジャーナリスト・横関寿寛)